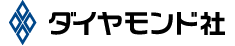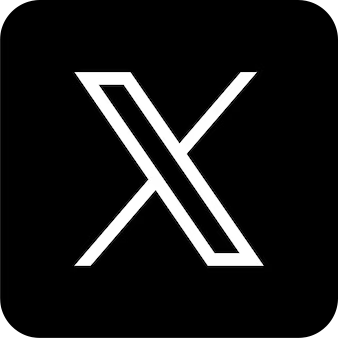「職場のメンタルヘルス」を強化する

「職場のメンタルヘルス」を強化する
書籍情報
- 吉野聡 著
- 定価:1760円(本体1600円+税10%)
- 発行年月:2016年01月
- 判型/造本:46並製
- 頁数:256
- ISBN:978-4-478-06821-2
内容紹介
ストレスチェック制度によって、職場のメンタルヘルス改善は管理職の義務となる。労働時間を削減しても、メンタルヘルスは向上しない。みんなが生き生きと働き、成果を上げる職場にするために不可欠な「予防・成長型メンタルヘルス対策」を詳細に解説する。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
第1章 改善されない「経営課題」としてのメンタルヘルス
【第1章の概要】
1-1 誤ったメンタルヘルス対策に振り回される職場の苦悩
メンタルヘルス対策の効果が「ある・あった」とする事業所は36.9%しかない
メンタルヘルスは職場の健康度に影響を与える「経営課題」である
1-2 事後配慮型メンタルヘルス対策の問題点
職場のメンタルヘルス対策の4類型
職場復帰の判断は職場が主体的に行う
配慮は有限かつ計画的に行う
復職時には再発予防策をきちんと話し合う
必要なのは本人に内在する本質的な問題に向き合う作業
1-3 職場で増え続ける不適応型メンタルヘルス不調
メンタルヘルス問題の原因や中心的症状の変遷
職場で増え続ける「不適応型メンタルヘルス不調」
「不適応型メンタルヘルス不調」が増える背景は何か
職場環境の変化に加え働く価値観の多様化も
1-4 誤った職場対応がメンタルヘルスに対する理解を阻害する
主治医の診断書に潜む危険性
指揮命令に従える状態にまで病気を治すことが会社員としての責務
メンタルヘルス不調を特別扱いする必要はない
column 中高年のメンタルヘルス不調の特徴
column 主治医から見た産業医
【第1章のまとめ】
第2章 メンタルヘルスに対する職場での正しい理解
【第2章の概要】
2-1 正常と異常の境界線
月曜日の朝「会社に行きたくない」と思うのは異常なのか?
うつ病と診断されるには「2週間以上の症状の継続」が必要
2-2 労働災害事案と私傷病事案の選別
職場で絶対的に避けなければならないストレスとは?
労働災害の判定はどんな基準でなされるか
2-3 職場における事例対応判断の視点は疾病性ではなく機能性・事例性
判断のポイントは職務遂行能力が発揮できるか・支障が生じていないか
管理職が気にかけるべきは部下がどの程度業務を遂行できるか
職場のメンタルヘルス対策は職場全体の心の健康度を上げるための施策
2-4 安全配慮基準の適切な理解
本人の希望通りの配慮は必ずしも有益ではない
メンタルヘルス不調者に「がんばれ」は禁忌か
メンタルヘルス問題を特別な健康問題にしない
ケーススタディ 〜もしも部下からこう言われたら〜
column メンタルヘルス不調は遺伝するのか
column 精神障害における「障害」の意味
【第2章のまとめ】
第3章 コストから投資に変えるメンタルヘルス対策の考え方
【第3章の概要】
3-1 メンタルヘルス対策は重要な経営課題
メンタルヘルス問題と企業業績の関係性
プレゼンティズムとアブセンティズム
果たしてストレスは悪者なのか?
3-2 労働時間を削減してもメンタルヘルスは向上しない
日本人の労働時間はОECDの平均を下回っている
労働生産性の低さをいかに改善していくかがメンタルヘルスの最重要課題
長時間労働でもメンタルヘルス不調者のいないベンチャー
主観的存在としてのストレス
予防成長型のメンタルヘルス対策の勧め
【第3章のまとめ】
第4章 ストレスを前向きに捉える人材の育て方
【第4章の概要】
4-1 ストレスに強い人と弱い人は何が違うか
物事の捉え方によってストレス反応は変わる
健康な体に健康な精神が宿る
4-2 睡眠時間と抑うつ度の関係
睡眠時間が5時間を切っている人はその半数以上が抑うつ状態にある
ノー残業デーは確実にリフレッシュできる時間を生み出す
4-3 ストレスに上手に対処できる人の共通点
SOC=首尾一貫感覚とは何か
SOCを構成する3つの要素
SOCの感覚を自分なりに意識して過ごす
4-4 論理と情緒のバランスを重視した育成
前向きな人を育てる叱り方 後ろ向きな人を量産する叱り方
竹のような強くしなやかな人材を育てる
サポート活用力を前向きに評価する
【第4章のまとめ】
第5章 ストレスを職場の活性化につなげるマネジメント方法
【第5章の概要】
5-1 部下の能力を引き出すための人材マネジメントの必要性
低成長期に求められる心理的報酬
産業構造が変わり仕事の価値観も変わった
名プレーヤー必ずしも名監督にあらず
5-2 裁量権を与え、達成感を味わわせる
相手の気持ちも尊重するアサーティブなコミュニケーション
ストレス増強要因よりもストレス緩和要因を意識する
5-3 ストレスチェック制度を活用した職場マネジメント
ストレスを良好なレベルにコントロールする
ストレス要因が大きくても心身のストレス反応が小さい「活性職場」
5-4 一度メンタルヘルス不調に陥った人を再活性化する方法
職場には見逃してはならないメンタルヘルス不調のサインがあふれている
部下の不調に早期に気付き勇気を持った決断を
大前提は「誰でも心を病むことはある」
【第5章のまとめ】
おわりに
著者
吉野 聡(よしの・さとし)
吉野聡産業医事務所代表、新宿ゲートウェイクリニック院長。
2003年筑波大学医学専門学群卒業、2007年筑波大学大学院人間総合科学研究科修了。
東京都知事部局健康管理医、浦和神経サナトリウム精神医師、筑波大学医学医療系助教・附属学校教育局統括産業医を経て、2012年に吉野聡産業医事務所を設立。2015年には新宿ゲートウェイクリニックを開院。