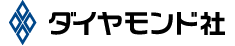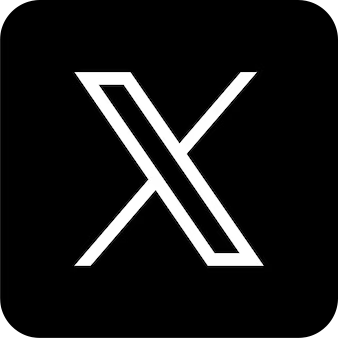しらずしらず
あなたの9割を支配する「無意識」を科学する

しらずしらず
あなたの9割を支配する「無意識」を科学する
書籍情報
- レナード・ムロディナウ 著/水谷 淳 訳
- 定価:2200円(本体2000円+税10%)
- 発行年月:2013年12月
- 判型/造本:4/6上製
- 頁数:392
- ISBN:978-4-478-02094-4
内容紹介
なぜ、同じ姓というだけで好意を抱くのか? 人が何かを決めたり、行動したりする時、そこには必ず「無意識」の働きが存在し、しかもその影響力は、知覚、感情、記憶、コミュニケーション、社会活動など、ありとあらゆる面に及ぶ。あなたを知らず知らずのうちに操る「無意識」の働きを解き明かした「心の科学」の決定版。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
プロローグ
サブリミナルな世界が持つ、強大な影響力
心理学を科学にした新技術、fMRI
無意識を解き明かす旅へ
第 Ⅰ 部 「あなた」を支配する無意識
第1章 なぜ同じ名前というだけで好意を抱くのか?
── 「無意識」の知られざる影響力
カメに「心」はあるか?
意識と無意識、2つの脳
ホロコーストの生存者に見る、無意識の支配力
「脱フロイト」する心理学
スミスさんはスミスさんと結婚する?
味すら自分で判断していない? ── 「サブリミナル効果」の本質
BGMひとつで揺らいでしまう「合理的な意思決定」
脳は経験をつくりだす ── 「ペプシパラドックス」
発音しやすい名前の企業が成功する? ── 「流暢さ効果」
雨の日のトレーディングにはご注意を
無意識の力が、日常を支配する
第2章 視力を失ったのに表情が見える?
── 「五感」だけでは何も感じられない
心理学は「科学」といえるのか? ── 先駆者たちの奮闘史
人類は無意識で生き延びた
膨大な視覚情報を(寝転びながらでも)処理できるのはなぜか?
失明した脳卒中患者TNは、なぜ表情が「見えた」のか?
「盲視」で明らかになる無意識の力
T中佐の苦悩 ── 見えないのに、動いていることだけがわかる
「視野闘争」実験 ── 無意識もポルノ好き?
イスラエルで味わった、「虫の知らせ」を信じるべき理由
盲点、サッカード、弱い周辺視力 ── 知覚はすべて錯覚か?
無意識は「音」も勝手に補う ── 「音素修復」
日常世界を「モデル化」する脳(そしてそれは信用できるのか?)
第3章 なぜ、「目の前の人物が入れ替わっても気づけない」ことがありうるのか?
── つぎはぎだらけの歪んだ「記憶」
トンプソンを襲った2重の悲劇
「記憶違い」が生む数えきれぬほどの「無実の罪」
人間テープレコーダー vs 本物のテープレコーダー
記憶 ≠ ハードディスク
「授業中に起こった発砲事件」実験 ── 記憶は間違いだらけか?
記憶は無数の「でっち上げ」でできている
忘れられないとどうなるか? ── あるロシア人の苦悩
記憶はサムネイル ── ディテールは間違いだらけで変化する
9・11の日の記憶さえも
記憶は「伝言ゲーム」 ── 勝手に筋道がつくられる
そして、記憶は「滑らかに」なる ── 間違いに気づかないほどに
目の前の人物がすり替わっているのに……。 ── 「変化盲」
記憶を植えつけることは可能か? ── 過誤記憶
人生を首尾一貫して生きるための力は、無意識から生まれる
第4章 傷ついた心は「鎮痛剤」で癒やせる?
── 人も社会も無意識の「台本」で動く
88歳の母に見ぬかれた「ホーキングとの喧嘩」
生後6か月の赤ん坊でも、親切/不親切を理解する
「ジルスタイン博士」の2つの実験
心の痛みは薬で抑えられる? ── 社会的苦痛と肉体的苦痛の関連性
ヒトを人にした「心の理論(ToM)」
志向性 ── ヒトを他の霊長類と分けるもの
脳の大きさと社会集団の大きさは比例する?
「6次の隔たり」で世界がつながる
無意識を担う脳は、ヒトもウサギも変わらない?
絆を育む「オキシトシン」という魔法
信頼ゲームとオキシトシン、そして社会的行動
心理学と無意識の微妙な関係
理由があれば何でもいい? ── 脳の「台本」を暴く
fMRIはなぜ革命的な成果をもたらしたのか?
ヒトを形づくる3つの脳 ── 爬虫類脳、辺縁系、新皮質
「社会神経科学」の誕生
第 Ⅱ 部 「社会」を支配する無意識
第5章 なぜ「作り笑い」はすぐにバレるのか?
── コミュニケーションを支配するのは「言葉」ではなく無意識
算数のできる馬「クレヴァー・ハンス」論争
接し方で成績が変わる? ── 非言語的コミュニケーションの力
事前に抱いた予想は、人知れず伝わってしまう
子育てへの教訓 ── 親の期待が子をつくる
非言語的なコミュニケーションはなぜ必要か?
「作り笑い」は無意識には通用しない
ボーイフレンドが見せた無意識の「タイサイン」は何を示す?
見つめる時間でわかる、優越性と序列
身振り手振りだけで感情を見抜けるか?
非言語的コミュニケーションの3つの型を活かすには
第6章 「顔」で選んで投票してしまうのはなぜ?
── 「見た目」と評価のダイレクトで密接な関係
「恋は機械じかけ」に反論できるか?
コンピュータに感情を見出す
相手が人間であろうとなかろうと
女性が好きな「ヒトの鳴き声」とは?
「声」で首相に登りつめたサッチャー
タッチするかどうかで恋は決まる
ケネディvsニクソン、勝負を分けたのは?
選挙は「顔」で決まる?
かくも強い無意識の影響力とそのメリット
第7章 なぜ、ガンディーもリンカーンも「同じ過ち」に陥ったのか?
── 分類が先か、ステレオタイプが先か
「分類」という奇跡の能力
カテゴリー分けがもたらす致命的な「不具合」
ヒスパニックは怠け者か? ── 固定観念
九死に一生を得たユダヤ人心理学者が見出した「無意識の偏見」
あなたの偏見をあぶりだす「潜在的連合テスト(IAT)」
ガンディーやリンカーンも抱いていた「分類に基づく偏見」
意識的な努力により、無意識の力を正しく活かす
第8章 なぜマックユーザーとウインドウズユーザーは互いにいがみ合うのか?
── 意味などなくても生まれる「派閥」と「差別」の正体
ロバーズ洞窟の決闘騒ぎ
いとも簡単に生まれる「自分たち vs 彼ら」
内集団での決め事が、個人の知覚を形づくる? ── 「集団規範」
たった1つの共通点でも生まれる「身びいき」
「黒人」という単純化に潜む問題
女性は本当に数学が苦手か? ── 帰属意識が能力を変える
公共広告の「ポイ捨て禁止」キャンペーンは、なぜ逆効果で終わるのか?
犬好き? マック派? ── 違いは何でも構わない
9・11で体験した「ニューヨーカー」の優しい力
第9章 幸せな「ふり」があなたを幸せにする?
── 「感情」は、感覚と環境でつくられる
人はみな多重人格 ── 「不変の感情」という虚構
偽の手術で痛みが消える? ── プラシーボ効果
「感情とは何か?」 ── 謎めいた心理学者ウィリアム・ジェームズの貢献
生理が先、感情が後 ── 「感情の錯覚」
脈拍が上がるから(性的に)興奮する
幸せな「ふり」が人生を充実させる
秩序を追い求め、何とか理由をこじつける「左脳」
決断の理由はいつも「後づけ」?
知らず知らずのうちに社会的規範に基づいて判断してしまう
「心のしくみ」を知るメリットとは
第10章 なぜ「楽観的すぎる」締め切りを設定してしまうのか?
── 「自己」という歪んだレンズと、その活かし方
「ハリケーン・カトリーナ」と自分を正当化する人たち
なぜCEOは4割も高く企業を買収してしまうのか?
3人の「キリスト」を一緒に生活させると
心は科学者か弁護士か ── 「動機づけられた推論」
ひいきのチームの反則に気づけない ── 動機が知覚を歪める
ビッグバン理論を受け入れない学者たち
自己欺瞞のゲームから抜け出すために
人は「見たいもの」を見る ── 温暖化否定派の都合のよい解釈
なぜ納期を楽観視してしまうのか?
隠れた性差別がいまも横行するわけ
公平を自認する不公平な心
ジョブズの「現実歪曲空間」と成功者の条件
それでも無意識は役立っている ── 前向きな「錯覚」で人生を豊かに
謝辞
解説 サブリミナルを耕す ── 茂木健一郎
注記
索引
著者
レナード・ムロディナウ(Leonard Mlodinow)
1954年アメリカ生まれ。カリフォルニア大学で物理学の学位を取得後、マックス・プランク研究所フンボルトフェローを経て、現在はドイツ・マックスプランク研究所とカリフォルニア工科大学(カルテック)で数理物理学を研究している。一方で、難しい科学的内容を誰にでも読める文章にする才能に秀でており、物理学をはじめポピュラーサイエンスの本を多数書いている。その他、スティーブン・ホーキング氏の著作のライターも務めている。
著書に、世界的なベストセラーとなった『たまたま──日常に潜む「偶然」を科学する』のほか、『ユークリッドの窓』(日本放送出版協会)、『ファインマンさん最後の授業』(メディアファクトリー)、『ホーキング、宇宙と人間を語る』(共著、エクスナレッジ)など。
「スタートレック ネクストジェネレーション」や「冒険野郎マクガイバー」といったテレビドラマの脚本を手がけたこともある。
[訳者]
水谷淳(みずたに・じゅん)
翻訳者。東京大学理学部卒業。博士(理学)。主な訳書に『数学の秘密の本棚』(イアン・スチュアート、ソフトバンククリエイティブ)、『論理ノート』(D・Q・マキナニー、小社刊)、『頭のでき』(リチャード・E・ニスベット、小社刊)、『歴史は「べき乗則」で動く』(マーク・ブキャナン、早川書房)、『物理学天才列伝』(ウィリアム・H・クロッパー、講談社ブルーバックス)などがある。
「無意識」を知れば、苦手なことも克服できる!?
あの『ヤバい経済学』を超える知的興奮がこの1冊に!
茂木健一郎氏解説!
「脳内ビッグデータ=無意識を
使いこなすための最高の本だ!」
あなたは自分自身のことをどこまでわかっていますか?
知らず知らず人を支配する無意識の謎に迫る!
・あなたがある人を好きになるかどうかを決めるのは、「名前」だった!
・1日でできると思ったのに3日かかった……。
・目の前で話している人が入れ替わっても気づけない!?
もしこんなことを言われても、多くの人が「自分に限ってそんなことはない」と言うのではないでしょうか。
ですが、その「思い込み」こそが、無意識の影響力の強さを物語る証拠でもあります。
なんと無意識は、人間の記憶、感情、知覚、コミュニケーション、社会活動といった広い範囲にわたって巧妙に影響を与えているのです。
本書は、上記のような一見「ありえない」と思われる人間心理を明らかにした魅力的な実験や事例に、著者自身のエピソード——買うつもりのないペルシャ絨毯を買ってしまった話から、9・11に巻き込まれて実感したことまで——を交えて、私たちが、いかに無意識という私たちの心の「見えない部分」に、「知らず知らずのうちに」翻弄されているのかを解き明かしていきます。
まさに心の科学の最先端であり、「決定版」とも言える本です。
科学書+エンタメ+人生の教訓!
『たまたま』で絶賛された傑出したサイエンス・ライター、ムロディナウの最新作
本書をより魅力的にしているのが、著者であるムロディナウ氏の類まれなる取材・執筆力です。
カリフォルニア工科大学(カルテック)で教鞭をとる傍ら、サイエンス・ライターとしても活躍しているムロディナウ氏は、あの車いすの天文学者、ホーキング博士のライターも務める(過去にはハリウッドで脚本も書いていた)という才人。
前著『たまたま——日常に潜む「偶然」を科学する』(小社刊)も、全世界20か国以上でヒットしました。
今回、無意識というテーマを書くにあたって、あのDNAの二重螺旋構造を発見し、その後意識の研究に邁進したクリストフ・コッホ氏のもとで研鑽を積み、自らも被験者になったりと体当たりで取材して執筆しています。
そんな彼の著作の大きな特徴は、無意識についてただまとめた本にはなっていないことがあります。
どうすれば無意識の「支配」から脱し、よりよく無意識の力を使っていけるか、という「知識の活かし方」にもページが割かれているのです。
つまり、そのまま読めば「無意識」にまつわるおもしろくてためになる科学書、よくよく読めば「無意識に振り回されずに生きる」ための指南書、という「エンタメ性」と「人生の教訓」を両立したサイエンス・ノンフィクションなのです。
無意識を「脳内ビッグデータ」と喝破!
茂木健一郎氏の解説「サブリミナルを耕す」にもご注目ください!
いまや心の科学に、脳についての研究は不可欠ですが、その最前線も描く本書の日本語版の解説を執筆してくださったのは、日本における第一人者、茂木健一郎氏!
未処理のデータが蓄積され続ける無意識を、「脳内ビッグデータ」とたとえ、無意識の働きを知ることで「苦手を克服できる」とする本解説は必見です!