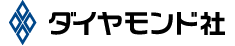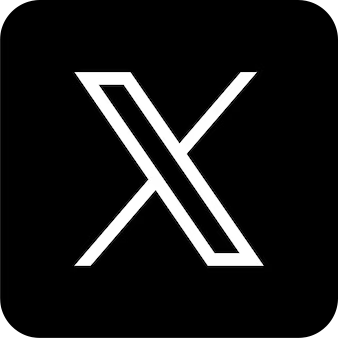経済は地理から学べ!【全面改訂版】
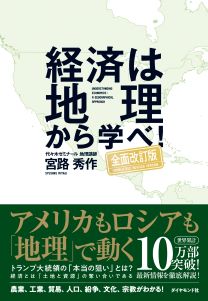
経済は地理から学べ!【全面改訂版】
書籍情報
- 宮路 秀作 著
- 定価:1870円(本体1700円+税10%)
- 発行年月:2025年04月
- 判型/造本:46並
- 頁数:328
- ISBN:9784478121115
内容紹介
「トランプ大統領再び! ”強いアメリカ”の行方とは?」「アメリカVSロシア——北極海航路を巡る経済戦争」「資源の輸入から読み解く、日本の生存戦略とは?」激激動する世界情勢に対し、各種データをアップデートし、今と未来をつかむための視点を徹底解説! 7万人が絶賛した地理本がパワーアップ!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに 地理がわかれば、経済ニュースがもっとわかる!
序章 経済をつかむ「地理の視点」
NO.01 自然:地球が人類に与えた「土台」とは?
NO.02 スケール:大きく見るか? 小さく見るか?
NO.03 資源:なぜ奪い合いが起きるのか?
NO.04 距離:経済は「4つの距離」で動いている!
NO.05 関係性:因果関係と相関関係は違う!
NO.06 視点:普遍性と地域性を同時に考える!
NO.07 思考:物事は複線的に考える!
第1章 立地 地の利で読み解く経済戦略
NO.08 日本の経済戦略は「資源の輸入国」から〝先読み〟できる
NO.09 地の利を活かした「インドのシリコンバレー」
NO.10 「1枚の地図」で読むロシアとヨーロッパの経済的つながり
NO.11 イギリスのEC加盟がアジア・太平洋に与えた「影響」とは?
NO.12 経済発展のカギは低賃金!? 先進国スペインの〝地の利〟
NO.13 インド、タイ、メキシコ。最強の自動車生産体制を探る
NO.14 経済大国のキーワードは「1位機械類、2位自動車」である
NO.15 北半球の重要拠点、アンカレジ空港が持つ地理的優位性
NO.16 カスピ海の原油を巡るパイプライン敷設の〝落としどころ〟
NO.17 今や自動車生産王国! インドネシアの「地の利」とは?
NO.18 温暖化で得をする国がある? 北極海航路の未来
第2章 資源 資源大国は声が大きい
NO.19 「水道水が飲める国」資源大国としての日本
NO.20 日本は資源大国⁉ 海底資源を巡る隠れた攻防
NO.21 資源戦争! 中国VSオーストラリア・ブラジル
NO.22 希少資源、レアメタルが生んだ悲劇とは?
NO.23 アルミニウムがわかれば、資源大国がわかる
NO.24 チェチェン今昔物語 ── 大国ロシアに翻弄される「火薬庫」
NO.25 資源大国ブラジルに見る「安定」資源とは?
NO.26 EUに加盟しない実力国、ノルウェーの正体
NO.27 ダイヤモンド国家ボツワナの「3つの地理的悪条件」とは?
NO.28 電気自動車が戦争の引き金に? エネルギーを巡る駆け引き
NO.29 フランスがニューカレドニアにかけた圧力の正体
第3章 貿易 世界中で行われている「駆け引き」とは?
NO.30 トランプ大統領再び! 彼が目指す世界とは?
NO.31 日本のEPAに学ぶ「本当のWin—Win」とは?
NO.32 オーストラリアの稼ぎ方 ── 豊富な資源を自国利用しない
NO.33 物理距離は3500㎞! アメリカは木材を買う? 売る?
NO.34 ブラジルとヨーロッパを結ぶ意外な産業とは?
NO.35 中国の14億人を支える食料とその危うさ
NO.36 中国が投資を急ぐタンザニアのポテンシャル
NO.37 半導体とブロックチェーン ── 米中テック冷戦の行方
第4章 人口 未来予測の最強ファクター
NO.38 土地も資源もない日本が、なぜ経済大国になれたのか?
NO.39 人口の増加に欠かせない2つの要素とは?
NO.40 人口大国の共通点は「5つの農作物」
NO.41 人口、GDP、貿易額で比較! 最強の国家群は?
NO.42 なぜ人々は東京に集まるのか?
NO.43 日立市の人口が減って、豊田市の人口が増えた理由
NO.44 少子化と高齢化を別々に考えるべき理由とは?
NO.45 一人っ子政策の廃止 ── 中国経済の光と影に迫る
NO.46 「高度人材」が次々生まれるスウェーデンの移民政策
NO.47 インドとブラジルの合計特殊出生率が示す深刻な問題
NO.48 合計特殊出生率だけではなく、完結出生児数も知っておくべき理由
NO.49 ドイツのガストアルバイターに見る多文化共生の難しさ
第5章 文化 衣食住の地域性はなぜ成り立つのか?
NO.50 シンガポールの強さの秘訣は「みんな仲良く」
NO.51 ソーセージ、ジャガイモ、ビールは天の恵み
NO.52 イギリス料理が「マズい」といわれる本当の理由
NO.53 世界をリードするニュージーランドの酪農
NO.54 美味しいワインは「気候」から生まれる
NO.55 牛乳とバターの生産量は世界一! インドを支える「牛」の力
NO.56 日本人は、なぜ「日本人」と称されるのか?
おわりに 時代が変われば、「正解」が変わる
巻末資料 「背景がわかれば、統計は面白い」
著者
宮路秀作(みやじ・しゅうさく)
代々木ゼミナール地理講師。日本地理学会企画専門委員会委員。鹿児島市出身。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座と高校教員向け講座「教員研修セミナー」の講師を担当する「代ゼミの地理の顔」。一部の講師しか担当できないオリジナル講座も任され、これらの講座は全国の代々木ゼミナール各校舎・サテライン予備校にて配信されている。「地理」を通して、現代世界の「なぜ?」を解き明かし、さらに過去を紐解き未来を読むことで景観を立体視する講義は、9割以上の生徒から「地理を学んでよかった! 」と大好評。講義の指針は、「地理とは、地球上の理(ことわり)である」。
著書『経済は地理から学べ!』(ダイヤモンド社)は海外翻訳本を含めると10万部を超えるベストセラーとなり、地理学の啓発・普及に貢献したとして、2017年度日本地理学会賞(社会貢献部門)を受賞。これまでに著書30冊を上梓した(海外翻訳・共著含む、監修本除く)。コラムニストとして、新聞・雑誌・Webメディアからの取材に対し、「地理学の面白さ」や「地理教育の重要性」を広く発信。foomiiでのメルマガ配信や「Yahoo!ニュースエキスパート」への寄稿のほか、各種セミナーや講演会などにも積極的に登壇し、社会に「学び」を届ける活動にも力を注いでいる。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)