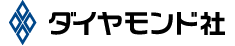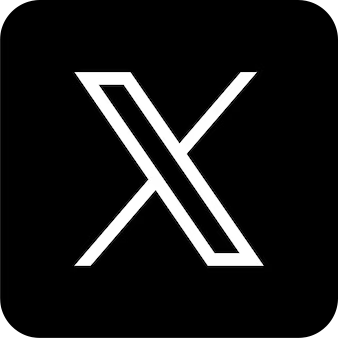感じがいい、信頼できる 大人の「ちょうどいい」話し方

感じがいい、信頼できる 大人の「ちょうどいい」話し方
書籍情報
- 松尾 紀子 著
- 定価:1540円(本体1400円+税10%)
- 発行年月:2024年03月
- 判型/造本:46並
- 頁数:224
- ISBN:9784478118856
内容紹介
幼少期から極度のあがり症で引っ込み思案だった著者が、アナウンサーとして試行錯誤を繰り返しながら活躍した32年間の局アナ生活で得た知見を紹介。フジテレビアナウンストレーニング講座の講師としても活躍。信頼できそう、仕事が出来そう、説得力がある、などの印象を受ける「大人にふさわしい話し方のテク」を紹介。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
プロローグ
はじめに
● 学芸会でセリフが言えなかった私が、アナウンサーに
●「ちょうどいい話し方」は、自分も相手も大切にする話し方
●「ちょうどいい話し方」は人生をよりよくする魔法の道具
第1章 ちょうどいい会話の7つの基本
ちょうどいい会話の基本1 大事なのはテクニックより感情のやり取り
● 自分も相手も大切にするのが「ちょうどいい」
● 背伸びをしすぎず、等身大の自分で
ちょうどいい会話の基本2 「お互いの価値を増やすため」を目的にしよう
●「価値を増やす」ためだから、気に入られなくたっていい
ちょうどいい会話の基本3 そもそもうまくいかないことだってある
● 人生もコミュニケーションも、50:50と考える
ちょうどいい会話の基本4 会話の心地よさは「聞き方」で決まる
● 聞くことは最大のコミュニケーション
● まずは、相手が話しやすい雰囲気作りを心がける
ちょうどいい会話の基本5 相手にとってちょうどいいリアクションをする
● 笑顔とアイコンタクトで安心感を与える
● リアクションには「大・中・小」がある
● 相手のノリに合わせたリアクションを
● あいづちは「同じ言葉」で返す
● 気の利いた言葉が出なくても気持ちが伝われば大丈夫
ちょうどいい会話の基本6 シンプルな「これだけメッセージ」を決める
●「今日の気持ちにタイトルをつけるなら?」と考えてみる
ちょうどいい会話の基本7 「会話泥棒」にならない
●「聞き上手な人」がやらないことをやめてみよう
コラム 「人をけなさず、自分をはっきり」
ニューヨーク支局で学んだアメリカ流コミュニケーション
第2章 ちょうどいい会話のコツ
● スキルよりも大切なのは「伝えたい気持ち」
● 言葉よりも、無意識の感情のほうが伝わっている
● 自分のありのままの気持ちを、相手に届ける方法
● 初対面の人との出会いを楽しめる3つの習慣
● 事前に、うまくいくイメージをする
●「成功するおまじない」を決めておく
● 体をほぐして、緊張を解く
● 相手に「快」を感じてもらえば、ちょうどいい「距離感」になる
● 相手を知ろうとする気持ちが最大の原動力になる
● 相手と距離を保ちたいときは共通の目的に集中する
●「もう一人の自分」から、自分を客観的・メタに見る
● 平常心に戻れる「合言葉」を決めておく
● 雑談は「話しやすいテーマ」で十分
● 相手の〝ツボ〟に入ったサインを見逃さない
● 雑談が苦手でも、「知識」があれば、大丈夫
● 話題を変えたいときは話を「受け止める」「要約する」
● 相手にも同じように意見・事情がある
● 感情的にならないために「受けとめて」から伝える
● ゆっくりとしたあいづちを打つと落ち着ける
● イヤなことを言われたら、「明るく切り返す」ほうが効果的
第3章 人前でちょうどよく話すコツ
● 自分の意見をちょうどよく伝えれば、人の心を動かせる
●「人前で話す時」は、「これだけメッセージ」を決めよう
●「人前で話す時」は3つの型のどれかでOK
●「聞き手と心でつながる」オープニングで好印象に
● クロージングは「これだけメッセージ」で余韻を残す
● 話のおさらいをすると共感が生まれる
● 聞き手に届くのは、「小学生にもわかる言葉」
● 苦手な言い回しを省いて「重荷」を軽くする
● 現場に持ち込む「原稿のサイズ」はA4 2つ折りに
●「はじめ」と「終わり」がよければすべてよし!
● 本番の直前は周りの人に話しかけよう
● 自分なりの方法で、ちょうどいい緊張感をキープする
● 第一声を大きめにして注目を集める
● 第一声は、笑顔でテンション高く
● 第一声の「第一音」だけ高い音を出す
● 話すときはNとZのアイコンタクトを意識する
●「まずい!」と思ったときの5つのリカバリー法
● 最後だけ視線を上げれば堂々として見える
コラム NYのプロフェッショナル・スピーカーの規格外の練習量
第4章 ちょうどいい話し方は「声」でさらによくなる
● 声の使い方で、人生はガラッと変わる
● 人の心を惹きつける“響く声”とは
● どんな声質でも響く声で話せる
● 響きが加われば、誰でもいい声になる
● 響きのある声は、扁桃体を刺激する
● 自分の個性を大切にして響きのある声を
● 抑揚を意識するだけで、「伝える力」が大幅にアップする
● 声にも「表情」がある
●「高く・低く」「速く・遅く」を意識しよう
●「抑揚」は「ハッピーバースデー」を歌うようにつける!
●「上虚下実」の姿勢で立ち姿もきれいに
● ゆるめすぎずに、適度なハリを
● 響く声を出す「上虚下実」の姿勢
● 声の大きさは「吐く息」の大きさに比例する
● 腹式呼吸は「お腹にある風船」を意識
● お腹、肩甲骨、胸周りの筋肉をストレッチでやわらかくする
● 1週間で体の変化が訪れる
● 響く声の秘訣は口の中の「高さ」にあり
● 高さのある空間では音が響く
●「自然体の地声」を意識しよう
● ハミングは、声を響かせる最高の発声練習
● 声は体という「楽器」に響く
● ハミングの喉の状態をキープすれば響きが加わる
● 楽しくハミングしてリフレッシュ
●「いい声」は後から身につけられる
● 必ずしも大きな声がいいというわけではない
● あごの力を抜くだけで「いい声」になる
●「あいうえお」には、正しい口の形がある
● 母音の口の形をマスターすれば滑舌はよくなる
●「声のベクトル」を意識しよう
● 相手の頭の後ろに届くような声の大きさで
● 一歩上の話し上手になるには、自分の声を聞きながら話すこと
● 3つのポイントを意識して、場面に合った話し方を
● 音読は、楽しく話す力を育んでくれる
● 音読は身近な文字なら何でもOK
● 練習すれば、必ず声と話し方は変わる
● 話せば話しただけ育っていく
●「声は人なり」その人の“あり方”が声に出る
● 言葉が自分を作り、人生を作る
おわりに
著者
松尾紀子(まつお・のりこ)
元フジテレビアナウンサー
自分を表現することにずっと苦手意識があり、幼少期は極度の緊張で話せず泣いてばかり。小学校の学芸会ではセリフのある役につけなかったほどだったが、「広い世界を自分の目で見たい」という思いから、1983年慶應義塾大学文学部卒業後、フジテレビに入社。
入社後、「モーニングワイドニュース&スポーツ」「スーパーニュース」「めざまし天気」「とくダネ!」などでキャスターを担当。1987年からフジテレビニューヨーク支局に特派員として勤務し、現地の日本語放送「おはようニューヨーク」のキャスターを務める。
アナウンス室初の女性部⻑、編成制作局アナウンス室専任局次⻑を経て、2015年早期退社し、フリーアナウンサーとして司会やナレーションを行う。
現在は、淑徳大学人文学部表現学科専任講師として「放送スピーチ論」、明治大学情報コミュニケーション学部と経営学部で「キャリア形成論」の授業を担当。フジテレビアナウンストレーニング講座「アナトレ」の講師として就活生にアナウンススキル、自己分析、自己PRなど面接対策を教えている。また、公立小学校で講師として「言葉の出前授業」を行うなど次世代の育成にも力を入れて活動している。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)