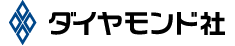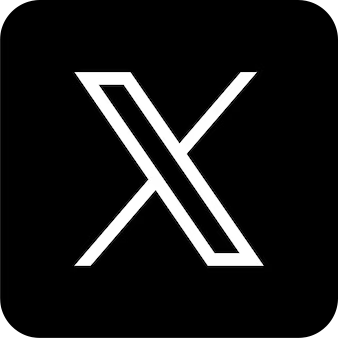対話するプレゼン
ロジカルなプレゼンより100倍説得力が増す方法
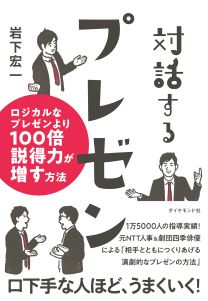
対話するプレゼン
ロジカルなプレゼンより100倍説得力が増す方法
書籍情報
- 岩下宏一 著
- 定価:1650円(本体1500円+税10%)
- 発行年月:2025年02月
- 判型/造本:46並
- 頁数:248
- ISBN:9784478118436
内容紹介
「対話するプレゼン」とは、相手とともに作り上げるプレゼンです。事前に決めたストーリーにこだわらず、柔軟に、相手に合わせる。緊張を和らげ、双方が本音で話せるプレゼン手法です。「ストーリー」「資料作り」「対話の方法」「問いかけの方法」「1対多の対話するプレゼン」について詳しく解説します
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
まえがき ロジカルなプレゼンよりも100倍説得力のあるプレゼンの方法があります
第1章 ヒアリングの進め方 〜プレゼン準備は「よく聞く」ことから始める
1 │ ヒアリングは4つのステップで行う
(1)相談にいたった背景について聞く
①相手が話しやすい質問をする
②背景についての質問をする
(2)問題について聞く
①現状についての質問をする
②理想の状態についての質問をする
③問題を絞り込む質問をする
④問題を特定する質問をする
(3)原因について聞く
①問題を生み出している原因についての質問をする
(4)解決策について聞く
①解決策についての質問をする
②納期と予算についての質問をする
第2章 ストーリーの作り方 〜「より良い未来」だけを考える
プレゼンにおける「ストーリー」とは何なのか
1 │ なぜ「桃太郎」の物語は記憶に残るのか?
2 │「問題解決」の考え方をマスターする
(1)背景の確認
〜桃太郎はいま村人が何を感じているのかを聞いてみた
①相談にいたった背景について聞く
(2)問題の特定
〜村人が何に困っているのかを洗い出してみた
②問題について聞く
(3)原因の特定
〜なぜ鬼が「金品を略奪する」のか、原因を特定してみた
③原因について聞く
(4)解決策の決定
〜桃太郎は、村人と議論を重ね4つの解決策を考えた
④解決策について聞く
第3章 資料の作り方 〜わかりやすくシンプルなデザインの資料を用意する
対話するプレゼンのための資料とは
1 │「対話するプレゼン」の資料はどこが違うのか
(1)シンプルなデザインと構成にする
①デザインに凝りすぎない
②構成を複雑化させない
(2)「対話」の余地を持たせておく
①プレゼン時間には1/3の余白を作っておく
(3)「?」が生まれない表現、言い回しをする
①あいまいな表現をしない
②同じことを表すのには必ず同じ言葉や言い回しを使う
③「秘伝のタレ」をそのまま使用しない
2 │ 対話を生み、迷子にさせない資料の作り方
(1)タイトルは「目的(何のために)」「提案(何をする)」を示す
(2)目次で問題解決への「道のり」を伝える
①ストーリーを整理できる
②資料の内容を最初に把握してもらえる
③どの部分の説明を聞くのか、選んでもらえる
④「いまどのあたりか」を確認してもらえる
(3)本編ページは「ページタイトル ─ 要点 ─ 詳細」の構成を守る
①各ページの内容が整理できる
②「つまり」から伝えると安心してもらえる
③プレゼンの時間を有効に使うことができる
(4)ページ数が多い時は中扉を入れる
(5)資料は大枠から作り、完成したら第三者に見てもらう
3 │ 実際の資料の例を見る
資料の例①【表紙】
資料の例②【目次】
資料の例③【提案の背景】
資料の例④【問題】
資料の例⑤【原因】
資料の例⑥【解決策その1】
資料の例⑦【解決策その2】
資料の例⑧【作業スケジュール】
資料の例⑨【費用】
資料の例⑩【その他】
第4章 プレゼン前の空気の作り方 〜お互いにリラックスして話すための空気を作る
プレゼンの5割は本番で作り上げる! 空気作り7つの秘訣
1 │ 空気作りの7つのアプローチを身につける
(1)感謝を伝える
(2)名刺交換で相手の名前の読み方を確認する
(3)目についたもの、気づいたことを褒める
(4)話しやすい話題を出す
(5)打ち合わせの終了時刻を確認する
(6)資料は空気作りが終わって本題に入る時に配布する
(7)本題の最初に「目的地(タイトル)」と「道のり(目次)」を示し、確認する
2 │ 空気作りのその他の効果を知っておく
(1)ささやかな、でも確かな最初の一歩が踏み出せる
(2)「あなたのことを尊重しています」が伝わる
第5章 話し方 〜生きた言葉と「間」で対話を生む
なぜプレゼンでは「生きた言葉」と「間」が重要なのか?
1 │「生きた言葉」で話す
(1)話す内容を丸暗記しない
(2)丸暗記せずに話す「半生話法」を使う
2 │「間」を味方にする
(1)「間」のとり方の基本を知る
(2)「間」の4つの効果を知っておく
①相手がアタマの中を整理する
②話し手自身がアタマの中を整理する
③質問を歓迎する姿勢を見せる
④ストーリーの構造を、言葉だけでなく体感時間で伝える
3 │ 相手を迷子にさせないように話す
(1)相手をよく観察する
(2)一人ひとりを均等に見る
(3)「現在地」を一瞬も逃さず相手と共有する
①資料のどこを見るべきかを常に伝える
②「話の流れを示す言葉」を使う
③「相手が」資料の該当箇所を見ているかを常に確認する
④「いま、山の何合目か」を示す
(4)短い意見を言う時などにも「目的地」「道のり」を示す
4 │ わかりやすい・聞きとりやすい話し方をする
(1)短文で話す
(2)結論から話す
(3)語尾に変化をつける
(4)適切なスピードで話す
(5)活舌良く話す
①「発音練習用テキスト」を使って練習する
②連母音の練習で一つひとつの音が聞きとりやすくなる
(6)声をきちんと届ける
第6章 問いかけと受けとめ 〜相手が話しやすい問いかけと受けとめでさらに対話を進める
プレゼンが上手な人ほど、相手に話してもらうのがうまい
1 │「問いかけ」を身につける
(1)「問いかけ」で対話はまわり始める
(2)プレゼン前に問いかける
①空気作りのアプローチを使ってプレゼン前に問いかける
(3)プレゼン中・プレゼン後も問いかける
①ページや章の変わり目で問いかける
②相手の意識が話し手の話に向いていない時に問いかける
③プレゼン後に問いかける
(4)もっと聞きたい気持ちにさせるよう問いかける
①相手が聞きたいことについて問いかける
②相手が続きを知りたくなるように問いかける
(5)やってはいけない問いかけと大切な心構えを知っておく
①相手を試したり、恥ずかしい思いをさせたりしない
②知らないことは素直に尋ねる
2 │「受けとめ」を身につける
(1)「受けとめ」モードに切り替える
(2)相手の言葉を引き出す技術を使う
①正しい姿勢をとる
②笑いたい気持ちがなくても、笑顔をうかべる
③「、」や「。」といった切れ目でうなずく
④自分が使いやすいあいづちを、適度にうつ
⑤相手の言葉をそのまま返す(「伝え返し」をする)
⑥相手の言葉を「要約」して話す
⑦相手の気持ちや感情を汲み取り、言葉で返す
(3)受けとめでも「間」を意識する
(4)知らないことは知らないと答える
(5)筋道を外れた場合は、相手と相談する
(6)時間切れが気になったら、進め方を確認する
第7章 1対多でのプレゼン 〜1対多の場面で「対話するプレゼン」を使いこなす
1対多の場面だからこそ活きるノウハウとは何か?
1 │「1対多プレゼン」と「ふつうのプレゼン」、どこが違うのか?
(1)たとえ相手が100人でも、一人ひとりと対話をする
(2)X字型、W字型のアイコンタクトをする
(3)会場の中に「味方」を作っておく
(4)魔法のあいさつで聞き手の心をつかむ
(5)「2段階の問いかけ」で聞き手との距離を近づける
①全員にクローズド・クエスチョンで問いかける
②個人にオープン・クエスチョンで問いかける
(6)プレゼン中・プレゼン後にも対話する
①プレゼン中に問いかける
②プレゼン後に問いかける
2 │ スライドを使いこなす
(1)スライドに向かって話をしない
(2)聞き手の視線をうまく誘導する
(3)スライドにプレゼンのペースを維持してもらう
3 │ 声を使いこなす
(1)良い発声をする
①腹式呼吸の練習で良い発声をする
②あくびの発声で豊かに響く声を出す
③聞き手に狙いを定めて声を出す
(2)マイクを正しく使う
①マイクは口の真正面に正対させる
②会場内に適正な音量で届いているか常に注意を払う
(3)声の4要素を理解して声を出す
4 │ 身体を使いこなす
(1)バレエダンサーのように美しく立つ
(2)ジェスチャーを取り入れる
①視覚的に理解を促進する
②話し手の言葉の輪郭をより際立たせる
(3)立ち位置でもプレゼンの内容を伝える
①話し手が主か、スライドが主かに合わせる
②内容に合わせる
③対話の相手の位置に合わせる
あとがき 対話をしながら、相手とともにより良い未来を創造する
参考文献
著者
岩下 宏一(いわした・こういち)
プレゼントレーナー、株式会社ビーユアセルフ代表取締役
鹿児島県生まれ。京都大学法学部卒業後、1993年にNTTに入社。人事部において新卒3000人採用の実務を統括。NTT分割再編成人事業務等を経て、NTTコミュニケーションズ株式会社の人事部立ち上げメンバーとなる。仕事の傍らミュージカルの専門学校に通い、2001年劇団四季オーディションに合格。俳優に転身し、ミュージカル「ライオンキング」ほか3作品500ステージに出演。退団後は、人材採用支援のレジェンダ・コーポレーション株式会社に入社し、コンサルティングマネジャーを経て人事部長となる。2014年に独立しプレゼン指導を開始、株式会社ビーユアセルフ設立。
日々、多くの人にプレゼン指導する中、真面目な人ほど「相手の気に入ることを話さねばならない」「間違えてはならない」などの思い込みでプレゼンに苦手意識を持っていることに気がつく。以来、縛られない、とらわれない、相手と率直に対話をするプレゼンを教えるようになった。官公庁、地方自治体、上場企業・ベンチャー企業、大学・高校等で今までにのべ300団体1万5000人以上に「対話するプレゼン」を教え、ラクに話せる、本音で話せる人たちを増やし続けている。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)