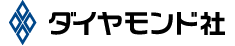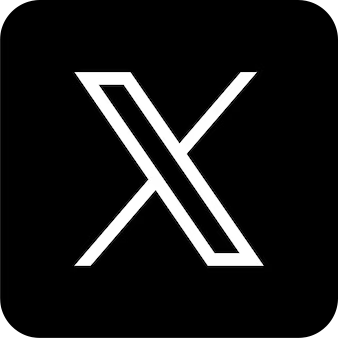金融デジタルイノベーションの時代

金融デジタルイノベーションの時代
書籍情報
- 山上聰 著
- 定価:1650円(本体1500円+税10%)
- 発行年月:2017年09月
- 判型/造本:A5並製
- 頁数:184
- ISBN:978-4-478-10372-2
内容紹介
銀行の未来はソフトウェア会社だ!近い将来、日本の金融機関は間違いなくグーグルやアリババと戦うことになる。先にやってきた崖っぷちを世界の金融機関はどう生き延びようとしているのか、日本の金融機関は何をすべきなのか。金融イノベーションの最前線を知り尽くす気鋭のコンサルタントによる現場報告と提言
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに デジタル自然淘汰の時代が始まった
第1章 激変する銀行の経営環境
(1)環境に適合したものだけが生き残る
(2)独り歩きするフィンテック
(3)銀行が自ら解決できる手段はデジタル技術だけ
(4)デジタル・トランスフォーメーション
(5)金融庁が進める改革
第2章 世界ではすでに金融秩序の破壊が始まっている
(1)銀行が直面する破壊的な瞬間
既存銀行に変革を迫る英国政府
(2)バンキング・ウーバー・モーメント
アントニー・ジェンキンスの警告/チャレンジャーバンクの登場/
共有される企業信用情報/消える銀行店舗
(3)政府が舵を取るシンガポールのイノベーション
国家主導型開発の歴史/行政と民間のフレンドリーな関係/
国家が直面するデジタルトランスフォーメーション
第3章 日本の金融危機が生んだ特殊な状況
(1)今も残る金融危機の爪痕
外科手術を拒んだ日本
(2)北海道拓殖銀行の破綻から学ぶ
官営特殊銀行としてのプライド/変えられなかったビジネスモデル/
インキュベーター路線の破綻/成功していたアジア戦略/
拓銀の破綻が教える代替案の必要性
(3)深刻な副作用を産んだ金融危機
コラテラル・ダメージ/強みの自己否定と連鎖/硬直化する企業組織
ダイナミズムが失われた社会/痴呆化する日本/リスク回避マインドの定着
(4)ITを外注化せざるを得なかった銀行
いち早くコンピュータを導入した銀行業界/システムアウトソーシングの副作用
(5)スウェーデンの金融危機と再生
Nordea Bankの誕生/自らを破壊せよ
(6)終わりを告げる昭和の金融
決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ/
新しい時代に入った金融行政/なぜ護送船団行政の撤廃が必要なのか
第4章 戦いを始めている世界の金融機関
(1)コミュニティ・デジタル化モデル
銀行で始まったデジタル・トランスフォーメーション/
金融危機が米国銀行に与えたダメージ/Wells Fargoのアプリ戦略/
顧客ビジネスのデジタル化支援/Lloydsのボランティア戦略/消費者のデジタル化/
Wells FargoとLloydsの共通点/スウェーデンとタイのキャッシュフリー戦略/
業界を挙げたSwishの開発/タイのナショナルeペイメント構想/
政府と業界が手を組んだスウェーデンとタイの改革/
さらに高まるデータセキュリティの重要性
(2)プラットフォーム・モデル
BNY Mellonの資産管理プラットフォーム戦略/
システムアーキテクチャーの革新とAPIの活用/業態によって変わるアプローチ/
これからの銀行の資産はテクノロジーとシステム開発者
(3)ハイタッチ・モデル
Umpqua Bankのハイブリッド戦略/デジタル・イノベーション・スタジオ/
ロボットによる接客/中小金融機関の顧客との接点
第5章 シリコンバレーの歴史にイノベーションを学ぶ
(1)シリコンバレーを創った男
きっかけを作った第2次世界大戦/テクノロジー業界を牽引し続けるムーアの法則/
ソフトウエアが世界を食べている
(2)アポロ計画とムーン・ショット
ケネディ大統領の宣言/Googleとムーン・ショット
(3)アメリカの新たなムーン・ショット“シンギュラリティ”と“収穫加速の法則”
第6章 人のイノベーション
(1)マインドを変える
経営者の世界観/デジタルにコミットする経営者/行員をデジタル化する/
イノベーション魂に火をつける/賞金付きコンテストで競わせる/
キッチンとピンポン台に見る新しいワークスタイル/行動規範とルールを導入する
(2)システム開発を変える
変化を抱擁するアジャイル開発手法/エクストリーム・プログラミングの手法/
チーム全体の士気を高めるペアリング
(3)スタートアップの支援
Y Combinator/Plug and Play
第7章 日本が直面する「今そこにある危機」
(1)切花から植林への処方箋
産業政策を変えた米国/テキサス州オースティンの成功/
シリコンバレーとオースティンの共通点/Barcleys銀行が支援したケンブリッジ現象/
シリコンバレーの優位性を築いたエコシステム/
地域がスタートアップと起業リスクを共有する/ニュージャージー州の失敗/
デジタル・イノベーションを成功させる3つの要因/日本の課題:イノベーションの構想/
ベルツの日本批判/切花から植林へ/抵抗勢力としてのフローズン・ミドル/
日本の課題:イノベーションの支援
(2)日本のウーバー・モーメントを乗り越える
ASEANが発するSOS/Alibabaの脅威/真の脅威と国難/データ錬金術
第8章 日本の金融機関が生き残るための2つの提言
もはや時間の余裕はない
(1)第1の提言:国境を超えたイノベーションのエコシステム
イノベーションの梁山泊を作る/ASEANへの期待/
最低水準となった日本の起業環境を打破/起業家をASEANに/
ASEAN発のスタートアップ/イノベーションを後押しする資金調達/
未公開株の取引市場を作る
(2)第2の提言:決済高度化を武器にイノベーションを推進する
イノベーションのコア領域としての決済業務/世界で拡がるリアルタイム決済/
APNHUBの実現とクロスボーダー連携/アジアの利害代表としての日本/
キャッシュフリー社会に向けたインフラを整備する/銀行の役割が大きく変わる/
社会インフラとしての認証機能/データ・ポータビリティのメーンプレイヤー/
顧客を守るという新たな使命
(3)ITベンダーのトランスフォーメーション
金融機関とITベンダーの競争が始まる/営業戦略の革新/
開発戦略の革新/ビジネスモデルの革新/Adobe Systemsの大胆な改革
(4)金融機関の未来像
デジタル金融プラットフォーム/目的が作る幸福
あとがき
参考文献
著者
山上聰(やまがみ・あきら)
1958年 北海道生まれ。NTTデータ経営研究所 研究理事、グローバル金融ビジネスユニット長兼シンガポール支店長。
立教大学経済学部卒業後、北海道拓殖銀行入行。ニューヨーク支店勤務などの後、外資系コンサルティング会社を経て現職。
金融審議会専門委員、XBRLジャパン理事、APN副議長、IPFAボードメンバーなどを兼任。金融ビジネス、決済、イノベーションに関する著作、寄稿、講演多数。
著書に、「決済サービスのイノベーション(共著)」、「XBRLによる財務諸表作成マニュアル(共著)」。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
- kobo
- kindle
- COCORO BOOKS
- Reader Store
- 紀伊國屋書店Kinoppy
- honto
- Booklive!
- セブンネットショッピング
- Google Playブックス
- Apple Books
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)