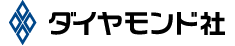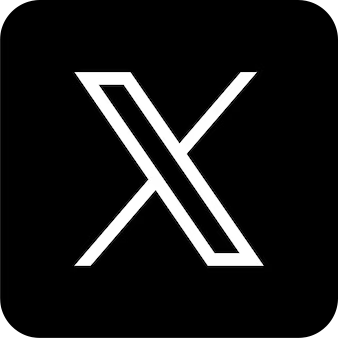知恵を磨く方法
時代をリードし続けた研究者の思考の技術

知恵を磨く方法
時代をリードし続けた研究者の思考の技術
書籍情報
- 林 周二 著
- 定価:1650円(本体1500円+税10%)
- 発行年月:2017年03月
- 判型/造本:46並製
- 頁数:312
- ISBN:978-4-478-10125-4
内容紹介
知恵の働きや役割は、科学や技術の領域においては勿論 のこと、日常的生活行動の場のなかでも決して小さいものではない。人のさまざまな知恵の搾り方、知恵の活用の仕方……知恵についてこれほどまでに深掘りした書はなかった。文系と理系を領域を越えて活躍する90歳博学の東大名誉教授がいま問う「日本人に必要な知」。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はしがき
起しの章
知恵の正体を考える
友とするによき者
定石的ならぬ創造的な生き方
Ⅰ章 二種類の知 ── 知識と知恵
Ⅰ章−1
知恵とはどのような知をいうのか
先人たちが僕たちに残した知
内知と外知
Ⅰ章−2
知識が肥大し、知恵の痩せた現代人
反比例の関係
知の不消化
Ⅰ章−3
生産性と創造性 ── 両者の役割の差
経済性と結び付き易い生産性
創造性なしに質的向上はない
I章−4
生産性追求が優先されがちの世相
二つの行動型
行動型と旅行
I章−5
人為的に作られる過度の一極集中
ベストセラー現象と日本
現代日本人の指示待ち傾向
I章−6
現代人が忘れている「自己責任」
自己責任には内知が必要
Ⅱ章 知識一般について
Ⅱ章−1
知識は無形の財産、精神の糧である
知識を活用する能力
脳みその食物
Ⅱ章−2
体系的な知識と非体系的な知識
日々脳内へ受容する非体系知
計算し尽くされ、降り注ぐ知識
Ⅱ章−3
体系知の修得には時間と費用が掛かる
現代人の身に付きにくい知
実証に基づく知に劣る日本
Ⅱ章−4
成人にとって体系知修得とその機会
休暇が知的格差を生むか
知識財投資の回収の巧拙
Ⅱ章−5
知的人間づくりの場は多様である
学校教育と国々
家庭教育の役割
Ⅲ章 知識から知恵への架橋
Ⅲ章−1
知恵は、知性と感性との共同作業から
知感覚、知感性
五感と知感覚
Ⅲ章−2
知恵の源泉としての諸知識
記録に残す術
強く関心を持つよう努める
Ⅲ章−3
各種の辞書類を引きこなす
各辞書の特徴を知る
言葉を介して文化への敬意を持つ
Ⅲ章−4
文章力を鍛えよう
良い文章の条件
文章上達法
Ⅲ章−5
知恵を紡ぎ出す読書法
どう読むか
古典を読む効用と読み方
Ⅲ章−6
知恵を生み出す旅行術
個人旅行の知的意義
旅の諸心得
Ⅳ章 知恵の諸側面
Ⅳ章−1
20世紀最大の知恵者エジソン
エジソンの知恵の源泉
理屈でなく実際の人
Ⅳ章−2
知恵の原点である知的好奇心
子供の知的好奇心の移り変わり
自分自身の手足を使う
Ⅳ章−3
良い知恵は「閃めき」から生まれる
どんな時に閃めくか
研究とゆとり
Ⅳ章−4
運に巡り合う才能──セレンディピティ
偶然の機会を自分のものにする力
幸運を手に入れるのに必要なこと
Ⅳ章−5
知恵のさまざまな形態
ユーモアは個性的表現の発露である
アドリブは突然閃めく一種の知恵
Ⅳ章−6
勘は日本人に固有な知の形式
勘を磨くための心掛け
知恵を借りるのも知恵
Ⅴ章 知恵を生む5つのアプローチ
Ⅴ章−1
「問題解き」よりも「問題作り」の訓練を
問題作りのうまい一流の人
問題の良し悪し
Ⅴ章−2
実物に触れよ。必ず現場を見よ
触れて試す重要性
五官を総動員する
Ⅴ章−3
比較考察して初めて納得できること
寺田寅彦の比較の視点
比較から生まれる新しい知的世界
Ⅴ章−4
視点を変えると景色も変わる
角度、切り口を変えよ
固定的な見方から自由になる
Ⅴ章−5
数値化、計量化してみよ
数値化の留意点
数字の独り歩きの弊害
Ⅵ章 知恵の担い手たち
Ⅵ章−1
文系の知恵と理系の知恵
文理の垣根にあるもの
文理の中間に第三の系を
Ⅵ章−2
専門の知恵と教養の知恵
専門人である前に教養人であれ
交流が求められている
Ⅵ章−3
玄人の知恵と素人の知恵
プロは目の付け所が違う
自由で偏りのないアマの視点
Ⅵ章−4
男性の知恵と女性の知恵
異性の発想、行動に学ぶ
多領域に研究成果が
Ⅵ章−5
地理人の知恵と歴史人の知恵
地理と歴史の学修比較
地理を軽んじがちな日本人
Ⅵ章−6
若者の知恵と老人の知恵
若者は自由度の広い分野へ
老人に必須の知恵
結びの章
索引(人名)
著者
林 週二
1926年(大正15年)生まれ。東京大学名誉教授、静岡県立大学名誉教授。統計学、経営学専攻。1948年、東京大学経済学部卒業。東京大学講師、助教授、教授(教養学部)を経て、静岡県立大学経営情報学部初代学部長、明治学院大学経済学部教授、そのほか、を経て一線を退く。賞罰なし。『マーケティング・リサーチ』(ダイヤモンド社、1958年)、『流通革命』(中公新書、1962年)、『現代製品論』(日科技連出版社、1973年)、『経営と文化』(中央公論社、1984年)、『比較旅行学』(中央公論社、1984年)、『現代の商学』(有斐閣、1999年)、『研究者という職業』(東京図書、2004年)等、著書多数。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
- kobo
- kindle
- COCORO BOOKS
- Reader Store
- 紀伊國屋書店Kinoppy
- honto
- Booklive!
- セブンネットショッピング
- Google Playブックス
- Apple Books
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)