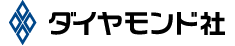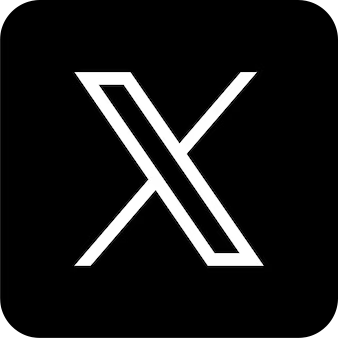立地の科学
購買行動を数値化する出店戦略

立地の科学
購買行動を数値化する出店戦略
書籍情報
- ディー・アイ・コンサルタンツ 著/榎本篤史 著/楠本貴弘 著
- 定価:1650円(本体1500円+税10%)
- 発行年月:2016年06月
- 判型/造本:46並製
- 頁数:216
- ISBN:978-4-478-06145-9
内容紹介
「通行量が多いのに流行らない」「駅前なのに売上が伸びない」「畑の真ん中にあるのに人気店」……その理由はすべて論理的に解明できる! 店舗売り上げの理由を「立地」の視点から科学的に解析し、見える化。店舗開発担当者のカン頼り、カリスマ経営者の独断といった、非科学的なプロセスに決別せよ!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
プロローグ
序章 すべての“立地”には、売れるためのストーリーがある
顧客の視点で歩けば、売れる立地が見えてくる
○3種の異質なエリアが、道一本で隣接する水道橋
○わずか30mの差で、明暗がくっきりと分かれるカフェと居酒屋
○どちらも「駅近」だが、立地の価値は雲泥の差がある
“非日常”のエリアだから必要になる日常の店 ── イベントエリアへ
○“非日常”の最たる場の入口に、なぜファミレスとコンビニが?
○毎回“初めて来る人”たちのために必要な店とは?
雑居ビルが密集する学生街、似合うのはやはりラーメン店?
○居酒屋、ラーメン、蕎麦屋、密集する街で盤石なのはやはりコンビニ
○小さいながらも実は経営は手堅い西口のカフェ
人が大勢いても店の運営・維持が難しいオフィス街
○成り立つか成り立たないかの指標は回転数 ── 飲食店
○オフィス街では難しい、じっくり顧客をつなぎとめるモデル
○突如、現れる大穴場の“立地”の可能性を引き出すには?
立地の科学・海外版
Column 01 “立地”の重要性はどの国でも同じ。だが、価値観の違いが如実に
第1章 街ゆく人の“無意識”を科学する
カンと経験に頼らない、科学的な出店基準の重要性
○人通りだけが、店の売上を左右するわけではない
○ハフモデルを超えて進化する売上予測
○商圏や通行量以外の要素をすべて使って「売上要因分析」を
○3つの分野への応用を
○多くの店を展開すればするほど利用価値が上がる「売上要因分析」
○カンと経験から科学へ ── 客観的な出店基準づくりの第一歩を
売上を決める「売上要因」
○「立地要因」と「商圏要因」の2つに分かれる各要素
○求める顧客が自然に集まる「顧客誘導施設」
○店は見えているか、知られているかの指標が「視界性」と「周知性」
○大勢の人が動く道を見つける ── 「動線」
○店は広いか、座席数は十分か ── 居心地の良い「建物構造」を
○物理的にも心理的にも良い「アプローチ」で入りやすく
○そもそもそこに十分な人口はあるか ── 「マーケット規模」
○目指す層の顧客はいるか ── 「商圏の質」
○店の目の前に人は通っているか ── 「ポイント規模」
○見落としがちな「自社競合」
○業界の垣根を超えて影響する「他社競合」
○チェーンによって全く違う“効く”要素
立地の科学・海外版
Column 02 海外独特の「売上要因」を早期に把握し、仮説・検証のサイクルで成功をつかむ
第2章 同じ通行量なのに売上に6倍の開き ── 「商圏の質」の謎を解け
神田は苦戦、中野は大繁盛の謎を解く
○「ポイント規模」は十分だが「商圏の質」を見落とすと……神田
○雑多な層をすべて受け入れられれば
○これだけ大学生がいるのに、なぜテナントはいつも入れ替わるのか?
競合するファストフードと地域スーパーマーケット
○デリバリー専門のファストフード出店が成功する土地とは?
○ファストフード出店でスーパーを調べる意味
扱う商品によってはスーパーと相性抜群のファストフードも
○実は晩のおかずだったあのファストフード
○同じチェーンでもテイクアウトとイートイン、デリバリーは全くの別業態
立地の科学・海外版
Column 03 日本以上に変化のスピードが早い海外では、柔軟で臨機応変な対応を
第3章 売上2.2倍にしたコンビニの最重要“要素”とは?
「アプローチ」と「視界性」の大幅向上で復活
○駅との間に割って入ってきた競合コンビニに対抗せよ
○脅威は徒歩客だけではなく、より広域に及んでいた
なぜ、標準化されたコンビニで売上に差がつくのか
○出店ルールを頑なに守って躍進するコンビニのトップチェーン
○エキナカという閉鎖商圏の膨大な「マーケット規模」を独占するニューデイズ
立地の科学・海外版
Column 04 各チェーンは適切な立地を求め、今も多様な実験を繰り返している
第4章 なぜか田んぼの真ん中で大繁盛 ── カフェを成功に導いた“要素”とは?
あれだけの顧客はどこから来るのか?
○朝は男性、昼は女性でいっぱい、土日祝日には家族連れも
○広い土地ゆえに「視界性」「周知性」「アプローチ」が大幅に向上
○くつろげる「建物構造」は長時間滞在を促し、追加注文にも
コンビニ跡地で躍進するリラクゼーションチェーン
○軽自動車の動きから読める「商圏の質」
○同じロードサイドでも、生活道路沿いという穴場をねらう
○リピートしやすい裏通りの店が実は繁盛店
○一度馴染みになってしまえば ── 先駆者により大きなメリット
立地の科学・海外版
Column 05 国特有の移動手段が理解できれば、適切な「商圏」を把握できる
第5章 読めれば成功、読み違えば打撃、変幻自在の「動線」を味方に
はるか先まで畑だけの土地のファストフード店
○実は2つの街の真ん中にあった抜群の「マーケット規模」
○強力な「動線」の存在によって成立する“立地”
変化を読み違えれば大打撃となる「動線」
○たった一本違うだけで大きな違いが
○地下鉄に新しい出入口ができただけで……
○広域に伸びた「動線」では、75㎞離れても競合が
立地の科学・海外版
Column 06 海外出店で頼りがちな「通行量」は、数の多さではなく“なぜ多いのか”を把握することが大切
終章 不振店・予算未達店“ゼロ”の予測はこうして実現する
売上を決める「売上要因」もう一度
○「立地要因」を構成する5つの要素
○人を惹きつける「顧客誘導施設」を見逃すな
○何より店を知ってもらう、覚えてもらう ── 「認知性」「視界性」「周知性」
○人が動く時にできる道を見逃さない ── 「動線」
○広い売り場や座席数で客数は大きく変わる ── 「建物構造」
○入りやすさにも科学的考察を ── 「アプローチ」
○まずはエリア内の人口の調査を ── 「マーケット規模」
○人口の中でターゲットとなる顧客を探せ ── 「商圏の質」
○店の前を歩いている人は? 走る車は? ── 「ポイント規模」
○最も強力だが忘れがちな「自社競合」
○意外な「他社競合」を見落とすな
自社独自の要素を見つけて「売上要因分析」を磨く
○チェーンによって全く違う“効く”要素
○データが集まれば集まるほど正確になる「売上要因分析」
○科学的な予測を磨くのは、泥臭い作業
会社で共有できる、科学的根拠のある出店戦略を
○立地戦略立案で本領を発揮する「売上要因分析」
○開発も運営も、数値的な根拠をもとにディスカッションを
立地の科学・海外版
Column 07 カンや経験に左右されず、数値を軸にした立地選びが、海外出店を成功へと導く
巻末付録 ラーメンチェーンはどのエリアで成功できるのか ── 出店シミュレーションの実際
ある地域に大量出店したい ── 立地戦略にこそ「売上要因分析」を
○既存店のエリアや店舗タイプによる傾向はあるか?
○既存店の傾向から、満たす条件を探し出す
○インタビュー、実地調査、あらゆる手段で“効く”「売上要因」を探す
○仮説と検証を繰り返して、売上を上げられる条件を明らかに
○条件を満たすエリアを、攻め込む地域にプロットする
○エリアが決まれば、その中で具体的な“立地”を決定する
○ドミナント出店に不可欠な高精度の予測は、「売上要因分析」だからこそ
著者
株式会社ディー・アイ・コンサルタンツ
ディー・アイ・コンサルタンツは、客観的なアプローチにより、店舗で生じているお客様の購買行動を分析・数値化することで、出店フローを統合的にデザインし、出店の拡大によって企業の成長に貢献することをミッションにしています。相互尊敬とチームワーク、多様な個性や知見、専門性の融合から生まれる相乗効果を大切にすると共に、クライアント企業との長期的な信頼関係の構築を重視します。
1991年創設
榎本 篤史(えのもと あつし)
㈱ディー・アイ・コンサルタンツ 取締役社長
小売業、外食、サービス業、生活関連サービス・娯楽業など、流通全般の成長支援プロジェクトに参画。クライアント企業との協働作業により、戦略の立案および実行を支援。
楠本 貴弘(くすもと たかひろ)
㈱ディー・アイ・コンサルタンツ マネジャー
小売業、飲食・サービス業、生活関連サービス業の出店戦略や売上予測の仕組み構築の立案・導入に豊富な経験を持つ。また海外での店舗展開支援に強みを持つ。