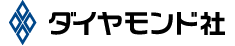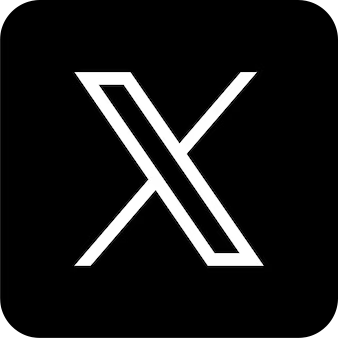だれも教えてくれなかった事業マネジメント
カネと意欲の管理がビジネスを育てる

だれも教えてくれなかった事業マネジメント
カネと意欲の管理がビジネスを育てる
書籍情報
- 佐藤 博:著
- 定価:1540円(本体1400円+税10%)
- 発行年月:2013年11月
- 判型/造本:A5並製
- 頁数:204
- ISBN:978-4-478-02601-4
内容紹介
会計屋がまとめる財務データは事業の死亡診断書でしかない。事業の構造を知り、改革を実践するためには、まったく違う発想の会計分析が必要になる。だれも教えてくれなかった事業の「生きた健康診断」のための分析と、そこから導き出されるマネジメントノウハウを初公開する
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
序 章 事業マネジメントとは 「カネ」と「意欲」の管理である
会計関係の書籍は「臨場感」がなく、事業現場では使えない
結果しか見ない会計屋は威張るな! 多くの会計資料は「死亡診断書」
第1章 「カネ」の管理
最低限必要な会計のポイントは3つ
売上高と利益
会社は利益を追求するためにある
会社活動の原点 売上高、売上総利益、そして事業の目的である営業利益
利益を左右する損益分岐点
損益表がわかっても事業の変化に対応できない
変動費と固定費に分けて費用構造を理解する
固定費と変動費では削減方法が違う
売上高の背景にある現実をつかむ
「カネ」の流れをつかむ
バランスシートはカネの流れを示している
累積の恐ろしさ、日々の大切さ
事業マネジメントに欠くことができないCCC
Column 会計の周辺知識と人の心
第2章 「意欲」の管理
意欲を高めるための仕掛け
その事業が利益を計上し、それが拡大する
その事業の予算を達成する
事業の中での自分の位置づけを1人ひとりが理解している
イソップ寓話の「3人のレンガ職人」
気配り、目配り、心配り
事実に忠実に報告する、ごまかさない
会社とは何か考えて見よう
Column 4つのコンプライアンス
コンプライアンス違反の現実
発生の背景
不正のきっかけ
売上債権(売掛金)の回収遅延
架空循環取引の発覚
スルー取引の怖さ
不正の発生のメカニズム
Column 不正のトライアングル
内部統制の仕組みによる不正の牽制や防止、早期発見
職場でのコミュニケーションを良くすること
Column 実は身近な金融商品取引法と内部統制
第3章 事業マネジメントの実際
現実の事業をざっと見る
1番大切な売上高と粗利益
性格の違うものは分けて集計する
現場の感覚を数字で見える化する
量販型事業(BtoC)マネジメントの手順
量販型事業(BtoC)マネジメントの実践
事業構造を分析する
問題点の把握と解決策
アクション
Column 現場から遠い本社
プロジェクト型事業(BtoB)マネジメントの手順
プロジェクト型事業(BtoB)マネジメントの実践
事業構造を分析する
アクション
すべて戦略は分析に始まる
Column 私の米国勤務体験 −その1−
第4章 利益分析のポイントと処方箋
競合会社とベンチマーキングする
事業マネジメントのための利益分析
事業のプロセス、担当部門の責任者を明らかにする
構造改革に必要な制度改革、組織改革を提案する
利益改善の処方箋
粗利益の最大化に向けた処方箋
変動費を削減する処方箋
固定費を削減する処方箋
コストダウンの秘訣は身の回りのコストを知ること
遅れているオフィス改革の視点と事例
第5章 収支改善の処方箋
売上高は代金の回収をもって完了する
不良債権の発生を抑えつつ売り上げを増やす
与信管理のための経営分析
すぐに支払ってはいけない債務
Column 私の米国勤務体験 −その2−
終 章 経理の研修をしていて思うこと
私が学んだ経理のフィロソフィー
軍馬の逃亡と経理
あとがき
著者
NECネッツエスアイ(株)執行役員CFO
佐藤博(さとう・ひろし)
1956年12月生まれ。79年慶應義塾大学経済学部卒業、2004年一橋大学シニアエグゼクティブコース修了。79年、日本電気(NEC TSE:6701)入社。以来、経理/財務、経営企画の業務を軸に経験を重ねる。NECの半導体グループカンパニー経理部長を経て、NECエレクトロニクス(現ルネサスエレクトロニクス TSE:6723)の上場責任者として2003年にIPOを手がける。以来、執行役員CFO。2010年にNECネッツエスアイ(TSE:1973)に移籍、執行役員CFOとして経理、財務、経営企画、関係会社管理、M&Aアライアンス、IR・広報を担当。1986年より3度の出向で在米経験は10年強。幾多の会計制度、経理システムの構築を指導、構造改革、経営改革を提案実行してきた。