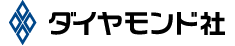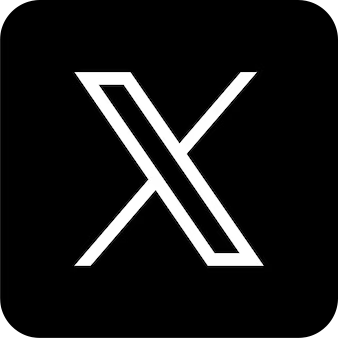戦略の経営学
日本を取り巻く環境変化への解
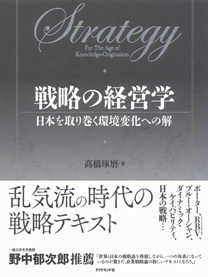
戦略の経営学
日本を取り巻く環境変化への解
書籍情報
- 髙橋 琢磨 著
- 定価:4620円(本体4200円+税10%)
- 発行年月:2012年12月
- 判型/造本:B5変並製
- 頁数:404
- ISBN:978-4-478-00381-7
内容紹介
ポーターを疑うことから、戦略策定をはじめよ。本書はポーター理論を紹介しつつ、時代変化、理論深化、数々の批判や新しい視点の登場によって、ポーター戦略論自体が変容せざるをえない状況を記述しながら、現代の世界および日本で求められる戦略の方向性と詳細を多角的に提示する。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
序章 ポーターの競争戦略論を疑え
創知・情報化時代の経営戦略論への助走
0.1 日本企業に戦略はなかったか
0.2 なぜ企業戦略論を学ぶのか
BOX:0-1 生物の適応戦略と選択、モンシロチョウの戦略と戦術
BOX:0-2 失われた20年と日本のICT産業
0.3 創知・情報化という時代認識
0.4 本書の構成
第1章 日本の対比で見る戦略論の展開
ポーターの競争戦略論は弱者の論理
1.1 ポーターの競争戦略論
品質とコストの限界線
業界分析から導かれたポジショニング理論
日米で対照的だった経営環境
1.2 日本企業の躍進が照らし出した企業戦略論の2つの系譜
創知・情報化時代の到来
アメリカではコア・コンピタンスを競争戦略論の対立軸として注目
1.3 戦略思考と企業の戦略
企業戦略論と事業戦略論を包摂した経営戦略論
1.4 経営資源と戦略の関係
経営資源の種類
1.5 企業戦略と経営環境の認識
企業戦略とは何か
環境変化への対応
第2章 ポーターの業界分析モデルの解体
デジタル革命がポーター理論に修正を迫るものは何か
2.1 企業を意味するバリューチェーン
2.2 直感によるSCPパラダイム
ポーターの5つの競争要因
ポーターの集中政策と企業のドメイン
2.3 業界構造
規模の経済と学習のもつ効用
業界構造の広がり:代替と補完を超えたインターネットの浸透
BOX:2-1 ドイツ経営学の貢献
2.4 独占禁止法と企業行動
業界の「正式」定義
独占禁止法の改正
BOX:2-2 業界を創造したヤマト運輸
リーニエンシーとゲーム理論
2.5 ニッチ戦略
アイリスオーヤマ
グローバル・ニッチ戦略
2.6 終わりに
第3章 分離したモノづくり、価値づくり
バリューチェーンのデコンストラクションの衝撃と戦略部品の経営
3.1 戦略部品の登場
モジュール化の衝撃
IBM互換機の起源とその帰結
スマイルカーブ
3.2 バリューチェーンの分解と再構築
BOX:3-1 モジュール化時代の終焉?
3.3 ファーストリテイリング(ユニクロ)に見る価値づくり
調達モデルで成功した第1ステージ
売上高1兆円企業を目指した第2ステージ:多品種・多店舗への果敢な挑戦
第3ステージの目標達成のカギ握るファッション性:中国市場
3.4 破壊的イノベーション
価値創造と価値獲得:ヌーコアと東京製鐵の違いに見る
3.5 終わりに
第4章 新技術・規制緩和が与える既存企業への衝撃
消えつつあるポーターの「先行者のメリット」
4.1 先行者のメリット
デルの在庫削減策
模倣の困難性
4.2 薄れてきたネットワーク外部性による優位
先行者利得が確保される環境条件
外部コンテクストを取り込んでいた日本の護送船団方式
ネットワーク外部性とネットワーク効果:直接ネットワーク効果と間接ネットワーク効果の違い
日本の携帯電話市場で検討するネットワーク外部性の妥当性
ゼロックスの特許の壁を破ったキヤノン
BOX:4-1 シスコの牙城を崩した華為技術
4.3 ブランドの終焉?
なぜブランド優位の重みが低下したのか
BOX:4-2 無印良品
日本の競争は先端か
多ブランド化の弊害除去に取り組んだユニリーバ
4.4 新技術の出現は新規参入者に有利か
ベンチャーの視点で機会を評価する
バイオ産業への参入
4.5 組立メーカーの復権を目指すパナソニックとキヤノン
ストロー型開発の功罪と日本の情報エレクトロニクス産業の危機
先行者利得の確保の困難性
なぜキヤノンはデジタルカメラで勝利したのか
4.6 終わりに
第5章 ドメイン価値を生かす集中と選択
「勝者のゲーム」である集中戦略はもろさと背中合わせ
5.1 集中に対応する規模の経済と範囲の経済
エアコンでパナソニックと対抗するダイキン工業
プロダクト・ライフサイクル論と集中戦略
5.2 ドメインとは何か
ドメインの3つの領域
BOX:5-1 後染め技術で飛躍したベネトン・グループ
ドメイン防衛策
5.3 ドメイン・マネジメント
キヤノン御手洗毅の先見
RISCチップの挑戦を退けたインテル
5.4 バリューチェーンでの集中:デジタル家電と量販店
量販店とプライベート・ブランド:デジタル家電のコモディティ化
量系列店から「スーパープロショップ」へ
5.5 ドメインの差し替え問題
富士フイルムのドメイン・チェンジ
BOX:5-2 TOTOの変身:トイレの匂いを消してキッチンへ
GEと日立製作所のドメイン戦略
5.6 終わりに
第6章 異次元の差別化を図るべき時代
「創異(difference-making)の経営」によるダイナミック理論の提示
6.1 ダイナミック企業戦略モデルの摸索
「ブルー・オーシャン戦略」
6.2 「創異」の経営戦略論
6.3 幅広く捉えられるべき「バーチュー・オリジネーション」
ブランド創設による価値創造
セイコーの成功と失敗
BOX:6-1 レクサスのブランド戦略
水平的差別化を追求するシャンプー市場
ダイアローグ型経営
6.4 「バーチュー・オリジネーション」(創美)の拡張としてのビジネスモデル
ビジネスモデルか、ビジネス・システムか
脇役の「戦略フィット」が主役の「ビジネスモデル」に
6.5 「ナレッジ・オリジネーション」(創知)をテコにした戦略部品の経営
「創知」のシンボルとしてのブレークスルー・イノベーション
オープン化とクローズ化を繰り返した自転車業界
シマノのマウンテンバイク:自転車ギア・システムという部品が製品そのもの
半導体製造装置に見るカール・ツァイスとASMLの分業
6.6 「創異」の経営における企業像
6.7 終わりに
第7章 学習を超えるナレッジ・オリジネーション
「まだ見ぬ」欲しいものを探り出し、創り出す組織の意味
7.1 野中のSECIモデル
小型化を担った複写ドラム:野中の知識創造
7.2 ブレークスルー型を受け入れる知的インフラとしての「場」
半導体製造装置に体化した知を無視した日本メーカーの没落
半導体製造プロセス:大見クリーンルーム仮説
知識二分法から知識地理学へ
7.3 ディベロップメント・ギャップ・マネジメント
産業化3つのフェーズ:科学主導・工学主導・情報主導の産業の登場
ハイブリッド車の成功に見る需要の再特定化
「アンダー・ザ・テーブル」の研究
7.4 活用型組織と探索型組織
アップルのオンライン・ミュージック事業
社内ベンチャーを生かす
7.5 創知・情報化時代のオープン化とネットワーク化
探索型組織の歴史的な展開
BOX:7-1 創知を分類し、イメージする
ネットワーク内部での協働の条件
イノベーションの創出とネットワーク経営:オープン・イノベーションの勧め
垂直統合企業モデルに今日的な意義はあるのか
デジタル情報主導の産業に見るネットワークの双方向性
7.6 終わりに
第8章 標準化戦略は脱ガラパゴス化現象策
差別化がアダになる標準化策を「軸足部品の経営」で乗り切る
8.1 新世代DVDに見る標準化の主導権争い
8.2 デファクト・スタンダードとデジュール・スタンダード
あいまいになるデファクトとデジュールの境界
ネットワーク外部性と標準化の意義
2つの標準・2つの経営
BOX:8-1 コモン・ロー(慣習性)にさかのぼるデファクト・スタンダード
8.3 軸足部品の経営:シスコシステムズと携帯電話のノキア
ルーターを軸足部品としたシスコシステムズ
携帯電話での標準設定の2つのガバナンス構造
ノキアの軸足部品経営を振り返る
8.4 終わりに:「軸足部品の経営」の前提としての
世界標準の設定を目指して
第9章 グローバル・ダイナミックスへの挑戦
少子高齢化時代の日本企業を襲う「後発者のメリット」
9.1 目指すグローバル市場とは何か
9.2 グローバルな課題を解決するための組織設計
グローバル企業の3つの類型
トランスナショナル・ソリューション
9.3 創知・情報化のインパクト
メタナショナル企業の出現
鉄鋼業界の企業形態の多様化
BOX:9-1 ゾーラン:本家メタナショナル企業
9.4 日本企業の多国籍化の特徴
9.5 下からの攻めで世界に君臨するグローバル企業
中国市場でトヨタのかんばん方式に立ち向かう新たなライバル
BOX:9-2 セブン-イレブンvs.ウォルマート
ダビニのエスカレーション・モデルによるサムスンの躍進
キャッチアップ型企業を押さえ込めなかった東芝
9.6 製薬業におけるグローバル化:目指すはアメリカ市場
ジリ貧の恐れ大の日本企業
国際化の中で創知型企業となった武田薬品工業
武田薬品のアメリカ事業の再編
9.7 終わりに
第10章 価値づくりに照準を合わせた組織と企業
デジタル化で分解された組織をコーディネートする
10.1 デジタル化の進展が企業組織や企業の境界に与えた影響
企業組織へのインパクト
企業の境界へのインパクト
取引コスト理論とガバナンス構造
10.2 企業組織の構造とプロセス
組織とインセンティブ
プロセスとは
組織構造
コスト・センターとプロフィット・センター
10.3 ナレッジ型企業モデルで組織を見る
学習する企業と市場シェア
組織と戦略と意思決定
10.4 企業のガバナンス構造と戦略
法人実体説が有効な日本の企業
分離の時代に垂直統合が行われる意味
10.5 「安定的な企業は不安定」というパラドックス
成果主義と年功序列制の功罪
組織の柔軟性と統合性
10.6 企業変身策としての出島政策
10.7 終わりに:自己回帰的な組織の見直し
第11章 高まる買収・アライアンスの役割
──日本でも始まったM&A戦略の時代
11.1 企業買収の目的と分類
11.2 買収の事前検討と事後対策
IBMのHDD事業を買収した日立の誤算
被買収企業になるという選択、独立するという選択
11.3 資本市場の発展と企業買収の活発化
1980年代のアメリカとの対比
企業買収をめぐる攻防策
11.4 買収を廉価に代替しうるアライアンス
内部開発、買収、アライアンスの比較
鉄鋼業におけるアライアンスと買収攻勢
BOX:11-1 海外の合弁に見直し機運
業務提携も選択肢
11.5 段階を追って選択肢を選ぶ
シスコシステムズのA&D戦略
身の丈にあった買収を成長戦略に取り入れているテルモ
プラズマ・ディスプレー・パネル(PDP)での松下電器と東レの合弁事業
11.6 終わりに:事例より学ぶ買収とアライアンスのあり方
第12章 多角化戦略と本社の役割
シナジー効果をどう確保するか
12.1 企業の成長志向と多角化
PPM理論
ビジネスモデルの拡張性
BOX:12-1 コングロマリット・プレミアム
12.2 ブラザー工業のバリューチェーン・マネジメント
創造業への革新政策
「飛び石戦略」の成功要因
まったく新規のLED事業で成功を収めた豊田合成
多角化をめぐる経営者のエージェンシー問題
注目された業界要因
12.3 財閥の形成と企業の情報優位
12.4 戦略的波及効果と競争優位の確立
スキル移転での本社の役割
シナジー効果の追求
12.5 複雑化への対応としてのマトリックス組織
マトリックス組織の提唱
ABBによるマトリックス組織の採用
ABBによる成長へのシフトとマトリックス組織からの離脱
マトリックス組織の今日的意義
12.6 終わりに
終章 企業戦略の品格とは何か
CSP(コーポレート・ソーシャル・パフォーマンス)の提唱
13.1 ミッション・ステートメントの意義
13.2 CSPとは何か
ナイキの失敗から学ぶ
ナイキの処方箋と多様なアプローチ
13.3 CSPの枠組みをどう考えるか
「世間」と異なる近代社会
BOX:13-1 安心と信頼
近代社会における守りの倫理、攻めの倫理
BOX:13-2 トヨタ事件とジョンソン・エンド・ジョンソンの信条(クレド)
13.4 CSPの受身的側面とリスクマネジメント
ウォルマートの憂鬱とCSP
危機を乗り切ったブリヂストン
ブリヂストンの成り立ちと今日
アメリカへの進出とファイアストンの買収
ブリヂストン-ファイアストン(B-F)のタイヤリコール問題
企業理念とブランド・ビジョンの策定
13.5 攻めの倫理としての社会的な目標への挑戦
メルクのCSPへの転換
NPOとの協力で企業が医薬を開発するパターン
13.6 終わりに
索引
著者紹介
髙橋琢磨(たはかし・たくま)
1943年岐阜県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。カリフォルニア大学バークレー・ハース校修了(MBA)。2007年、中央大学大学院商学研究科〈論文博士〉。1966年野村総合研究所入社、金融調査室長、ロンドン支店長、経営開発部長、研究創発センター主席研究員。2000年北海道大学大学院客員教授、2002年中央大学大学院教授を経て、現在は明治学院大学非常勤講師、国際協力機構(JICA)の政策投資案件に関し、第1次〜第4次の株式処分評価委員会委員長を務めている。著書に『マネーセンターの興亡』(日本経済新聞社)、『戦略部品への挑戦』(日本経済新聞社)、『金融はこれからどう変わるのか』(金融財政事情研究会)、『中国市場を食い尽くせ』(中央公論新社)、『知的資産戦略と企業会計』(弘文堂)などがある。