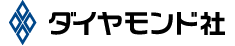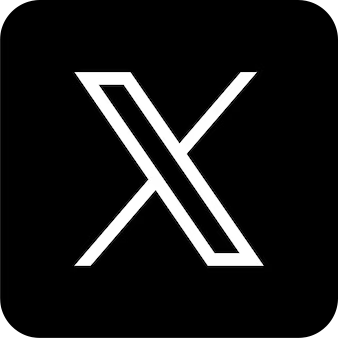第一人者が明かす光触媒のすべて

第一人者が明かす光触媒のすべて
書籍情報
- 藤嶋 昭 著
- 定価:2420円(本体2200円+税10%)
- 発行年月:2017年11月
- 判型/造本:A5並製
- 頁数:256
- ISBN:978-4-478-10160-5
内容紹介
東海道・山陽新幹線「のぞみ」の光触媒空気清浄器、成田国際空港の光触媒テント、丸ビルの光触媒タイル、パナホームの一戸建、日光東照宮の防カビ、光触媒蚊取り器など、日本発のクリーン技術として光触媒は急ピッチで普及。2017年度「文化勲章」受章、ノーベル化学賞候補による書きおろし!光触媒の基本から最新事例まで完全図解!発見50周年の永久保存版!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
第1章 なぜ、光触媒は広がり続けているのか?
1-1 光触媒の広がり
無限の可能性に気づき始めた人たち
光触媒国際研究センターが研究拠点に
抗カビ効果を活かした「日光東照宮・漆プロジェクト」
ジャパンオリジナルの漆器も
1-2 光触媒の医療への応用
手術室への活用が年間数百室
がんや「手足口病」にも有効
世界初の食中毒予防と“光触媒蚊取り器”
予防こそ最大の治療! ホワイトニングやインプラントにも
1-3 光触媒のアグリ・バイオ分野への応用
農作業の効率化や低コスト化
太陽光を室内へ
虫歯予防や抗がん作用の「希少糖」ができる
1-4 快適な暮らしを支える光触媒
ホテル、病院、介護施設、保育園、中古車業界でも可視光で使える高感度光触媒が活躍
花粉症対策マスク、抗菌ボールペン、カーペットにも普及
「シラス」を活用した防汚コーティング剤
2020年東京オリンピックから宇宙開発まで
Column 光触媒、ついに検定教科書に登場!
第2章 いま、住宅や高層ビルにも光触媒が大人気の理由
2-1 住宅の外壁は汚れない「光触媒タイル」が新常識
丸ビルで日本初の光触媒タイル! 1000億円市場が活気を帯びている
住宅の美を創造・維持する光触媒タイル
光触媒タイルの住宅はNOxを除去
2-2 高層ビル、工場、教会の外壁で活躍する建材・コーティング材
TOTOが日本発の技術を世界へ
トヨタの工場でも2000本分のポプラに相当する空気浄化力
筆者自宅、岐阜大、ドイツ、中国、イタリア、どこでもピカピカ
美観維持と清掃コスト削減を実現したアルミ建材
掃除がいらないメガネドラッグの看板
2-3 テント膜材の可能性を広げた光触媒テント
東京ドームのテント膜材を作った会社
「4つの特長」とテニスコート、フットサル場、バッティング練習ドーム
八重洲口「グランルーフ」、ダラス10万人スタジアム、フランスで活躍するテント材
クフ王のピラミッドでも光触媒が!
2-4 汚れない、曇らないガラスでクリアな視界をキープ
節水に成功した「セントレア」と理科大の“曇らない”ガラス
ルーブル美術館や学校にも光触媒セルフクリーニング強化ガラス
2-5 建物内の可視光で活躍する光触媒
「可視光応答型」光触媒による内装用ガラス
世界初! 日本発の抗菌・抗ウイルスガラス
抗ウイルスカーテン、高付加価値壁紙、ブラインド
室内の空気をキレイにする光触媒式空気清浄機
TOTOと筆者がトイレ問題に取り組んだ理由
光触媒除菌消臭器「ルミネオ」
Column 「3F」で行こう!
第3章 空港や新幹線にはどう普及しているのか?
3-1 空港、エアカーゴなど空の便を支える光触媒
中部国際空港内1万7000平方メートルのガラスに採用
インフルエンザウイルスに効果
光触媒が航空輸送に導入された世界初の取り組み
3-2 新幹線など鉄路を支える光触媒
セラミック製光触媒フィルターとは
「のぞみN700系」喫煙ブースで活躍する光触媒式空気清浄機
駅ホームの屋根材と白いテント材
「光触媒ペンキ」で駅舎をキレイに
駅構内のトイレにも応用
3-3 路面上と道路周辺をキレイにする光触媒
排水性を高める「高機能舗装」道路
路面上の空気をキレイにする「フォトロード工法」とは?
「NOx」除去で特別な維持管理が必要ない
トンネル内も渋滞回避! 光触媒つきトンネル照明器具
防音壁、道路標識、看板などロードサイドは宝の山?
「橋梁ラッピング」で高架下を明るく楽しい場所へ
「橋梁ラッピング」3つのメリット
トヨタ自動車の高級車に標準装備されたドアミラー
Column 発想の泉を枯らさない読書のすすめ
第4章 光触媒の「6大機能」と日常に広がる製品群
4-1 光触媒の「6大機能」とは
酸化分解力と超親水性
光触媒の「6大機能」とターニングポイント
一般住宅として世界初! 筆者の光触媒一戸建て
4-2 6大機能① 抗菌・抗ウイルス効果
耐性菌の急増、高まるウイルス感染症の脅威
細菌・ウイルスの不活化だけでなく有機物として分解除去
防汚・滅菌・防臭効果抜群の「光触媒タイル」
可視光でOK! 高い抗ウイルス性の「光触媒ガラス」
新千歳空港、ノイバイ国際空港で大活躍の「光触媒フィルム」
可視光応答型「粉末・スラリー」を使った「ルミレッシュ」と認証制度
3次元網目構造のセラミックフォームと空中浮遊菌除去装置
2次感染を起こさないのが最大のポイント
4-3 6大機能② 発想のコペルニクス的転回から誕生した「脱臭」効果
酸化チタンは、なぜ大量の物質分解には向かないのか?
“微量のものをターゲットに”というコペルニクス的転回点
紙・繊維製品・空気清浄機にも広がる理由
フィルターと光源をセットにした大型光触媒式脱臭装置
4-4 6大機能③ ガラスやミラーの表面が曇りにくい「防曇」効果
光触媒の超親水化現象とは
水との「接触角」と親水性
超親水性は接触角が「ほぼ0度」
曇りにくく、汚れにくい「超親水性」と「酸化分解力」の併せ技も
自動車のドアミラーと人命を守るカーブミラー(道路反射鏡)
4-5 6大機能④ セルフクリーニングを実現する「防汚」効果
来館者10万人突破の光触媒ミュージアム
「魔法の実験」への戸惑いと「水素博士」秘話
超親水性を体験する「光と水でキレイ」の実験
失敗と思われた結果を逆転の発想で実用化
ダブルの「セルフクリーニング効果」でコスト低減! 1000億円市場へ
4-6 6大機能⑤ 光で水をキレイにする「水浄化」効果
地球上に淡水はわずかしかない
コストをかけない安全な土壌地下水浄化システム
70基以上が活躍するADEKA総合設備の取り組み
レジオネラ菌もダイオキシンも分解! 環境にやさしい浄水装置
太陽光で農業廃液を処理! 稲作とトマト栽培も光触媒の時代
有機物除去率ほぼ100%で従来と同程度のトマトを収穫
魚市場の難敵「光回復現象」を防ぎ安全でキレイな海水を製造
4-7 6大機能⑥ 光で環境をキレイにする「大気浄化」効果
古代ローマ帝国のセネカも悩んだ大気汚染問題
NOxを除去し、コストも激減する画期的なシステムとは?
Column タンポポが“農夫の時計”といわれる理由
第5章 「人工光合成」の最新常識
5-1 資源・エネルギー・環境問題と光合成の仕組み
クロロフィル(葉緑素)が活躍する「Zスキーム」とは
化石燃料が抱える2つの問題点
5-2 水の光分解の感動と光触媒系の誕生
50年前に実験に成功した「光増感電解酸化」の仕組み
水の光分解の発見に至るおもな科学史
『Nature』に論文が掲載された理由
1974年元旦「朝日新聞」1面トップ、「朝日賞」「トムソン・ロイター引用栄誉賞」受賞
光触媒を定義する
酸化チタンから水素をとるには限界があるという発見
5-3 加速化する「人工光合成」の最新動向
太陽電池と水の電気分解のハイブリッド系
注目集まる「金属酸化物材料」
可視光でも水の完全分解! 「単一粒子型」と「Zスキーム型」の仕組み
日本がリードする二酸化炭素の還元・資源化
自然から学び、全体を俯瞰した最適解を
Column 「トムソン・ロイター引用栄誉賞」と論文の被引用数
第6章 反応機構と光のはなし
6-1 光触媒反応の主役は2つだけ
酸化チタン使用量がその国の文化レベルを表す?
酸化チタンの作り方
「硫酸法」と「塩素法」の仕組み
光触媒に使われるのは「アナターゼ型」
近紫外線を効率的に届ける常識破りの発想
6-2 酸化チタンは半導体の一種
半導体とは何か
「真性半導体」と「不純物半導体」
酸化チタンは光活性を持つn型半導体
6-3 酸化チタンのエネルギー構造と光照射の効果
半導体のエネルギー構造
バンドギャップとバンドギャップエネルギー
光触媒反応に影響を与える3因子
6-4 酸化チタンの結晶形態と光触媒活性
酸化チタンはどうやって発見されたのか
ルチル型とアナターゼ型のバンドギャップ値
アナターゼ型のほうが高い光触媒活性を示す理由
6-5 酸化チタン光触媒が利用できる光の波長とは?
可視光、紫外線、赤外線とは
酸化チタンの唯一無二性と普及が進む理由
6-6 強い「酸化分解」と「還元」の仕組み
酸化チタン表面で何が起こっているのか
酸化分解の仕組み
還元の仕組み
6-7 なぜ、「超親水性」が生まれるのか?
親水性とはっ水性の違い
酸化チタン表面の構造変化に注目
6-8 汚れない効果と曇らない効果の異なる仕組み
防汚効果の「光界面反応」と防曇効果の「光固体表面反応」
セルフクリーニングは2つの反応の併せ技
6-9 光触媒の多機能性が生まれる理由
なぜ、多業種から参入が相次ぐのか?
「本多・藤嶋効果」から生まれた3つの研究の方向性
Column 出前授業で科学の面白さを子どもたちへ
第7章 光触媒系の作り方
7-1 光触媒原料の形態とは?
酸化チタンゾル、チタンアルコキシド、酸化チタンコーティング液
7-2 2つのコーティング手法をどうやって活かすか
「ウェットプロセス法」と「ドライプロセス法」
コーティング法を選ぶポイント
7-3 コーティングのカギを握る接着層
光触媒反応を保護する重要なシリカの中間層
基材の劣化を防ぎ、密着性を高める「構造傾斜膜」
7-4 世界初の光触媒タイルはどうやって実現したのか
最も普及している光触媒タイル
光触媒と抗菌金属をハイブリッド化
外装用のセルフクリーニング建材への発展
7-5 光触媒ガラス、ドアミラーはこうしてできる
光触媒セルフクリーニングガラスの作り方
安全運転に寄与する「雨滴防止ドアミラー」
7-6 国際宇宙ステーションを浄化するUV - LED光触媒
光源と光触媒フィルターのモジュール化
UV - LEDが国際宇宙ステーションを浄化
国際的に急速に進むLED化
Column ガリレイ、ファラデー、パスツール、偉大な先人に何を学ぶか
第8章 光触媒技術の標準化、製品の認証制度
8-1 日本(JIS)と世界(ISO)で試験方法を標準化
JIS、ISOによる標準化の制定状況
海外の光触媒標準化に対する取り組み
8-2 オールジャパン体制へ! 光触媒製品の認証制度
健全な市場形成と普及への体制
試験方法の標準化に支えられている認証制度
安全性の基準と管理責任者の設置が義務
認証フローと認証後の監査活動
巻末資料 光触媒性能評価と光触媒ミュージアム
おわりに ── 中国古典の名言に学び、「死の谷」を乗り越えよう
参考文献
INDEX
著者
藤嶋昭(Akira Fujishima)
東京理科大学学長
1942年生まれ。1966年、横浜国立大学工学部卒。1971年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。1971年、神奈川大学工学部専任講師。1975年、東京大学工学部講師。1976〜77年、テキサス大学オースチン校博士研究員。1978年、東京大学工学部助教授。1986年、東京大学工学部教授。2003年、財団法人神奈川科学技術アカデミー理事長。2003年、東京大学名誉教授。2005年、東京大学特別栄誉教授。2010年、東京理科大学学長(現任)。
現在、東京理科大学光触媒国際研究センター長、東京応化科学技術振興財団理事長、光機能材料研究会会長、吉林大学名誉教授、上海交通大学名誉教授、中国科学院大学名誉教授、北京大学客員教授、ヨーロッパアカデミー会員、中国工程院外国院士。
これまで電気化学会会長、日本化学会会長、日本学術会議会員・化学委員会委員長などを歴任。
【おもな受賞歴】文化勲章(2017年)、トムソン・ロイター引用栄誉賞(2012年)、The Luigi Galvani Medal(2011年)、文化功労者(2010年)、神奈川文化賞(2006年)、恩賜発明賞(2006年)、日本国際賞(2004年)、日本学士院賞(2004年)、産学官連携功労者表彰・内閣総理大臣賞(2004年)、紫綬褒章(2003年)、第1回The Gerischer Award(2003年)、日本化学賞(2000年)、井上春成賞(1998年)、朝日賞(1983年)など。
オリジナル論文(英文のみ)896編、著書(分担執筆、英文含む)約50編、総説・解説494編、特許310編。