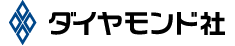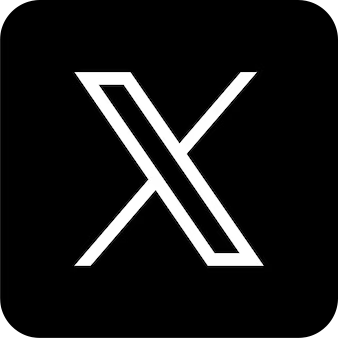儲かる会社は人が1割、仕組みが9割
今いる社員で利益を2倍にする驚きの方法

儲かる会社は人が1割、仕組みが9割
今いる社員で利益を2倍にする驚きの方法
書籍情報
- 児島保彦 著
- 定価:1760円(本体1600円+税10%)
- 発行年月:2017年03月
- 判型/造本:46並製
- 頁数:272
- ISBN:978-4-478-10146-9
内容紹介
利益を確実に生み出す会社にするための第一歩は、「人材などいない」ことを認めて「人材を欲しがらない」こと。そして「今いる社員のままで利益を出す方法を考える」ことです。つまり「人材に頼らない経営」ができれば、気づかぬうちに生じていた利益の流出を止めて、大幅な増益を実現することができるのです。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
序章 「人材」の幻想を捨てなさい
1 「人材がいないから」を禁句にする
そもそも「いい人材」など存在しない
中小企業にとっての「いい人材」は現場のリーダーのこと
大企業に中小企業で使える人材はいない
2 「いい人材」は中小企業の足を引っ張るだけ
「いい人材」が会社を壊すこともある
本当に必要な「番頭さん」は替えがいない
「いい人材」を育てても割に合わない
第1章 人材に頼らない組織に変える
1 「鶴の一声」型の組織にする
会社は社長の力量以上には伸びない
組織を変える覚悟を持ちなさい
和を重視する組織には弊害がある
人材における「2:6:2の法則」の意味
上位2割が「いい人材」だと錯覚してはいけない
下位2割の問題社員は分散しないで思い切って集めてしまう
中位6割の社員に当たり前の仕事をさせる
上位2割の社員の仕事は社長が引き取る
2 社員に「やったか」としつこく確認する
「当たり前」のことを「やらざるをえない」仕組みをつくる
結果をしつこくチェックしなければ意味がない
継続しか力にはならない
理解することと実行することは別ものである
共通の合言葉は「やるしかない」
3 PDCAの徹底は、人材に頼らない経営の基本
PDCAサイクルを意識して回せば人材は不要になる
目的と目標を明確に理解させてからスタートする
「to Do」を示して当たり前のことをさせるからメリットがある
「Check」はしつこく「やったか」を繰り返す
改善は、どうすれば行動しやすくなるかを考えること
PDCAを成功させるためには時間管理を徹底する
「1週間単位」を徹底する
第2章 全員がやらざるをえない仕組みをつくる
1 役に立たない「日報」を使える「武器」にする
常識破りの手法はここから生まれた
「訪問・日報・戦術・実行」のサイクルが回っていない
先輩から引き継いだ資産「釣り堀営業」
なぜ従来の営業日報は役に立たなかったのか
情報を中心にした新しい営業日報を目指す
「特になし」を禁止する
何を書いても決して非難しない
日報の真価を引き出す人材がいない!
「行動監視」ツールから抜け出せない
「人材に頼ってはいけない」「ないものねだりはしない」覚悟
2 人材の代わりに管理ソフトが会社を回す
人材に頼ってもダメなら、システムに頼ればよい
既存のデータベースを最大限に活用した、新しい営業システムを構築する
訪問先、訪問頻度は営業マンではなくてシステムが決める
2つ以上の視点を組み合わせることで、利益に直結する訪問を実践する
訪問先で行うべき営業内容を記号化する
情報を「煙情報」と「ホット情報」の2つに分類する
「煙情報」の共有が営業の質を根本から変える
日報での「情報」報告は1行ですませる
新規開拓を確実に実行させるシステム
新しく開発した営業管理システムの概要
日報はシンプルに記入できて、一目で読めることが基本
上司が電子日報を読まなければならないルールをつくる
管理者の「やったか」は社長がチェックする
営業システム構築の道のりは「忍耐」あるのみ
当たり前のレベルを徹底すると、社員の能力はそれ以上になる
3 人材に頼らない情報ネットワークを全部門に展開する
最終的には会計システムにまで連動させる
伝票・報告書の提出遅れはコンクールで解消する
第3章 有益な情報を引き出す2つの仕掛け
1 毎朝の20分ミーティング
デジタルな情報をアナログで補う
あまり役に立っていなかった従来のミーティング
必ず前日の課題のチェックから始める
否定、批評、「特にありません」は禁止する
ミーティングは1日も休んではいけない
管理者ミーティングで横のコミュニケーションをとる
2 仕上げは最も難しい「ホウレンソウ」
報告・連絡・相談が当たり前にできれば一流会社
「報告」は信頼関係を築く基盤となる
「連絡」は待つのではなく上から見つけて摘み取る
「相談」ができる雰囲気は「報告」「連絡」の徹底からしか生まれない
第4章 「利益をこぼさない」を追求すれば、収益は倍増する
1 そもそも利益はこぼれる、漏れるもの
2000万円の利益がゼロになるという見込違い
ほとんどの会社が赤字経営である背景
2 会社の中での「騙し」「ウソ」が利益を漏らしている
営業部門はこんな「ウソ」をつく
実態のない、言葉だけの「ウソ」を見逃さない
コンプライアンス教育は現場密着で根気強く
クレーム処理はスピードが命
「即開示すれば罪は問わない」の内規をつくれ
「内部告発」は止められない
利益が漏れる本命は、意外に多い「背任横領」
社長は銀行印を肌身から離してはいけない
3 売上は回収してはじめて売上高になる
売上代金を100%回収するためのルールをつくる
端数の切り捨ても見逃してはならない
信用管理はシビアすぎるほどシビアが鉄則
危ないと察知したら、思い切って顧客を見切る
売上を落とす恐怖は社長が一身に担えばいい
4 価格の決定権を営業マンに与えてはならない
業界の常識“安易な値引き販売”
安売りを禁止すれば、売上は伸びる
安売りの武器を取り上げれば、本来の営業に戻る
第5章 さらに利益を漏らさない3つのポイント
1 「日の当たらない事業」を棚卸すれば、意外な利益が生まれる
事業を洗い直せば、気づかなかった利益の源泉が見えてくる
部門間の序列にメスを入れなさい
2 無駄な会議は利益を漏らしている
会議は驚くほど高くつく
よい会議だったからといって、実行するとは限らない
会議は必ず「やったか?」で始める、そして社長の独演会にならないこと
時間になったら会議室の照明を消してしまう
会議は「出たくない」と言われるくらいでちょうどよい
3 利益を吐き出してしまう困った管理者
一見まじめな管理者が利益をこぼしている
管理者の評価は3つだけでいい
第6章 「人材に頼らない経営」は何を生み出したのか
1 社員が「なぜだ?」と思い「どうしたらできるか」を考えたら成功
人材に頼らない経営をすると、社員が考えるようになる
「わいわいがやがや」の社風になってくる
2 99%失敗する意識改革が今の社員で実現できる
意識改革には精神論や根性論は必要ない
「形」から入って定着させることが大事
3 社員への還元は「自利利他」の精神で
「人材に頼らない経営」へのステップ
根底に必要な考え方がある
報奨の評価は管理者との対話方式で
精神面での報奨も大切
おわりに
著者
児島保彦(こじま・やすひこ)
経営コンサルタント・中小企業診断士。1937年、長野県千曲市生まれ。1961年、早稲田大学商学部卒業。住友大阪セメント常務取締役、オーシー建材工業社長を歴任し、赤字会社を半年で黒字に転換。退任後65歳で経営コンサルタントとして独立し、有限会社祥を設立。
社長時代の経験から「会社は当たり前のことを当たり前にできれば、必ず利益は出る」ことを確信し、『プラス思考の社長学“当たり前”から始めてみよう!』(同友館)を出版。人材不足の中小企業に特化したコンサルティングで圧倒的な支持を受ける。
多くのクライアントの中には、大阪北新地の老舗ラウンジクラブoggi(オジ)もあり、夜の苛烈なクラブ経営のノウハウを昼間の経営の新しいヒントにしている。『ナイトクラブの経営にみる究極のサービス』(星雲社)、『本当は面白い戦略的出世術』(同友館)を出版。
71歳のとき、小妻清ホールディングスの社長に出会い、人材に頼らなくても今の社員で利益を倍増する仕組みを創り出し、実績を上げる。80歳を前にして、独立時に掲げた「サラリーマン時代の生涯収入を稼げるコンサルタント」を達成する。
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング、日本経営合理化協会、大阪商工会議所他講師を歴任。清泉女学院短期大学兼任講師、信越放送「儲かる会社の必勝法」のコメンテーター。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
- kobo
- kindle
- COCORO BOOKS
- Reader Store
- 紀伊國屋書店Kinoppy
- honto
- Booklive!
- セブンネットショッピング
- Google Playブックス
- Apple Books
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)