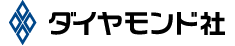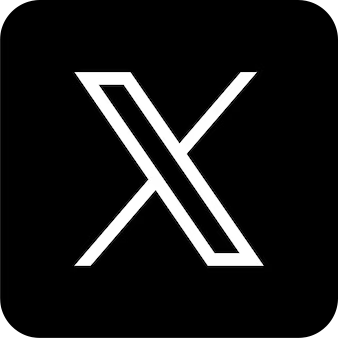「わかりやすい経済学」のウソにだまされるな!
経済学的思考を鍛える5つの視点

「わかりやすい経済学」のウソにだまされるな!
経済学的思考を鍛える5つの視点
書籍情報
- 益田 安良:著
- 定価:1760円(本体1600円+税10%)
- 発行年月:2013年03月
- 判型/造本:46並製
- 頁数:312
- ISBN:978-4-478-02290-0
内容紹介
マスメディアにあふれる、専門家と称する人々の「わかりやすい、明快な断言」。多くの人はそれを聞いて理解した気になってしまうが、実は経済における「わかりやすさ」には罠がある。実際の経済の複雑な因果関係を理解し、考えるための5つの視点と、どうやって経済を読み解いていけばいいのか、その処方箋を示す。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
わかりやすい議論には気をつけよう
「逆効果・反作用」がわかれば経済は面白くなる
本書が紹介する「5つの視点」とは
ポピュリスト政策にだまされないために
「風が吹けば桶屋が儲かる」式の論理だけでは経済は読めない
複雑な、ひねくれた経済の見方を身につけよう
教育現場でも有用な「5つの視点」
序章 「わかりやすい」経済論議には罠がある
1 なぜ政治家は耳障りの良いことばかり言うのか
2 「消費税率を上げなくても財政再建は可能」は本当か
3 耳障りの良い、わかりやすい話には2つの穴がある
4 「わかりやすさ」を求めすぎることの弊害
5 経済は「サルにもわかる」ほど単純ではない
6 「財政再建より景気対策」は最も深刻な耳にやさしいウソである
第1章 「わかりやすさ」にだまされないための5つの視点
1 複雑でわかりにくい経済を理解するための5つの視点
2 【第1の視点】合成の誤謬
立見席で2列目の観衆が背伸びをすると
経済における合成の誤謬の例
落語「花見酒」から学ぶ
3 【第2の視点】時間軸のずれ
短期的にはプラスだが長期的にはマイナスなもの
日本の景気対策は短期視点しか持たずに実施されてきた
金融・為替市場での短期・長期の意味
現実の金融市場は理屈どおりに動かない
現実の為替レートはいつも矛盾を抱えている
4 【第3の視点】セクターの違い
「誰の立場」に立って、「誰の利益」を高めるのか
世界と国家、国と地方の利害対立
産業間の対立、企業と家計の対立
5 【第4の視点】モラルハザード
すっかり有名になった「情報の非対称性」
情報格差がもたらす逆選択(adverse selection)
自動車保険の普及によって無謀なドライバーが増えた!?
6 【第5の視点】社会目的との相克
価値観の違いに根差す議論は永遠に折り合わない
日本では住宅取得に手厚い税制優遇があるが
社会目的と経済目的の衝突
経済格差の拡大は「経済的」には問題視すべきでない
子ども手当ての所得制限:社会目的と経済厚生との衝突
第2章 「消費税増税より景気対策が先」は正しいのか?
1 景気対策で本当に景気は浮揚するのか?
長期的な経済停滞と需給ギャップ・デフレ
短期的には効果があるが長期的にはマイナス
2 「日本は財政赤字でも大丈夫」は本当か?
「日本国債は90%以上が国内消化だから大丈夫」はウソ
国債金利はなぜ上がらないのか?
近い将来、経常収支赤字化とともにツケがくる
ドーマーの条件はなかなか満たせない
3 世代間の不公平は避けられない?
世代間の議論そのものが「時間軸のずれ」
富裕層と貧困層の資産格差は世代を超えて継承される
4 財政赤字はどうしたら減らせるのか?
拡張財政でどれだけGDPが増えるのか?
「上げ潮戦略」にだまされてはいけない
歳出削減の余地は小さい(無駄はなくせるのか?)
社会保障削減か増税のどちらを採るか
第3章 「金融緩和でデフレ脱却」は本当にできるのか?
1 日銀の量的金融緩和は経済を刺激するか?
銀行に資金供給してもマネーストックが増えないのはなぜ?
「時間軸効果」は確かにあったけれど
懸念すべきは金融機関のモラルハザード
正しい議論にはバランスシートでの理解が必要
日銀がリスク資産を増やさないかぎりマネーストックは増えないが
2 デフレ下でのインフレ率目標設定に意味はあるのか?
最終目標の物価を直接狙うのはしょせん無理
金融調節効果が経済に及ぶまでのラグ
金融政策の効果の非対称性(逆は真ならず)
3 為替レート誘導策に期待できるのか?
円高は日本にとって本当にマイナスか?
円高の影響は海外生産シフトのほうが深刻
デフレは短期的円安要因だが長期的円高要因
金融緩和で円安誘導は可能か?
為替介入の効果を過信してはいけない
円安への期待より円高対応に軸足を
4 日銀への過度の期待は禁物 地道に構造改革を
第4章 「TPPは経済復活の特効薬」は信用できるのか?
1 TPP(環太平洋パートナーシップ)協定を巡る混乱した議論
強い産業・輸出産業は推進、弱い産業・輸入競合産業は反対
田園風景の保護・食料自給率は経済学では処理できない問題
まず自由貿易に賛成か反対かを議論すべき
2 自由貿易はどんな利益をもたらすのか?
「王家が栄えて国滅ぶ」の愚
リカードの「比較優位論」が説く国際分業の利益
見えにくい自由貿易の利益と強烈な保護貿易への誘惑
輸出だけでなく輸入にも利益がある
「輸入関税」は実は経済に損失をもたらす
RCEPとTPPのいずれを優先するか?
「急がば回れ(長期的にはRCEPだが、まずTPP)」の観点で
3 産業空洞化は本当に起こっているのか?
円高のたびに進む海外生産シフト
産業の埋め合わせがあるかどうかが空洞化の鍵を握る
国際分業の下での強い産業育成と海外投資収益獲得に活路を
第5章 「雇用保護は労働者のためになる」は本当か?
1 雇用保護は労働者にプラスか?
リーマンショック後、ワーキング・プア、非正規雇用問題が急浮上
なぜ雇用保護がかえって雇用を減らすのか?
派遣労働の制限は労働者の味方か?
失業保険は不可欠、だがモラルハザードも
2 年金支給開始年齢引き上げのしわ寄せは若者に
年金制度改革は常に世代間の対立の火種
物価スライドとマクロ経済スライドの負担はどこに?
税方式にすべきか保険料方式にすべきか
専業主婦(第3号被保険者)の年金を巡る議論
定年延長と若年者雇用の減少をどう考えるか?
公務員の天下り防止は何をもたらす?
3 最低賃金と生活保護の複雑な関係
そもそも最低賃金はなぜ必要か?
最低賃金の地域格差が生活の地域格差を生む
生活保護制度との整合性をどうとるか
貧困問題、最低賃金、失業、生活保護、地域格差はすべてリンクしている
「生活給付付き職業訓練」が切り札
ヒントは英ブレア元首相の雇用ニューディール政策
終章 経済学的思考で探る日本経済再生戦略
1 真の経済構造改革とは何か?
「改革なくして成長なし」は正しいのだが
潜在需要を掘り起こすのは供給の役目
資源の最適配分をどう実現するか
政府が産業の有望分野を示すことの重要性
2 産業の過保護からいかに脱するか?
公益産業以外は救済の根拠がない
安易な企業救済の弊害
企業再生支援機構を常設にすべき
3 政府が中小企業を救済することは難しい
政府による中小企業向け金融拡充策の長い歴史
中小企業向け貸出が低迷する原因
中小企業を保護する根拠は何か?
4 産業の入れ替えをどう果たすか
規制緩和だけで産業は入れ替わらない
事業転換による需要掘り起こしが必要
外資の導入は産業改革の起爆剤
5つの視点をもとに抵抗勢力を退けうるタフな政策論議を
あとがき
参考文献
著者
益田安良(ますだ・やすよし)
東洋大学経済学部教授、同大学大学院経済学研究科教授
経済学博士
1958年生まれ。81年、京都大学経済学部卒業。同年、富士銀行(現みずほ銀行)に入行。88年に富士総合研究所(現みずほ総合研究所)に転出し、ロンドン事務所長、主任研究員、主席研究員などを歴任。2002年4月より現職、現在にいたる。
専門は、経済政策論、金融システム論、日本経済論。
主な著書に、『中小企業金融のマクロ経済分析』(中央経済社)、『反常識の日本経済再生論』『グローバル・マネー』(日本評論社)、『金融開国』(平凡社新書)、『グローバル・エコノミー入門』(編著、勁草書房)などがある。
ホームページ:http://www2.toyo.ac.jp/~masuda_y/plof.html
コラム:http://www2.toyo.ac.jp/~masuda_y/siten.html