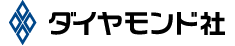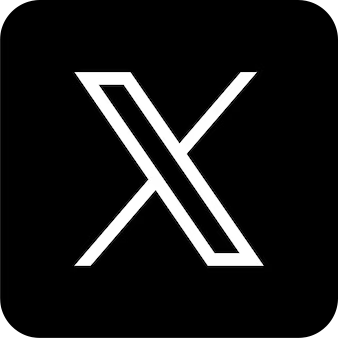たった10日で決算書がプロ並みに読めるようになる!会計の教室

たった10日で決算書がプロ並みに読めるようになる!会計の教室
書籍情報
- 林 總 著
- 定価:1650円(本体1500円+税10%)
- 発行年月:2020年09月
- 判型/造本:A5並
- 頁数:240
- ISBN:9784478108970
内容紹介
会計がわかるって、こういうことだったのか! ベストセラー『餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか?』著者の集大成となる会計の超入門書。決算書を通じて会社の健康状態を分析する技が、たった10日でわかってしまいます。会計の勉強で挫折した人も、これなら最後まで読める!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
日本人の会計リテラシーを底上げしたい
肥満の原因はカロリーではなく糖質の摂りすぎだった
第1章 なぜ、会計を学ぶの? 1日目
会計は基本さえ身につければ、簡単にマスターできる!
LECTURE01 複式簿記は人間の精神が産んだ最高の発明の1つ
●「会計は実学」 ── 使えないと意味がない
●会計の歴史
LECTURE02 複式簿記はお金の収支だけでなく、借入金と商品の増減も同時に管理できる
●素朴な疑問
●3つの会計公準
●企業実体の公準(公私混同を禁じる)
●貨幣価値評価の公準(決算書は金額で表わす)
●継続企業の公準(会社は永遠に潰れない)
COLUMN1 会計期間とビジネスサイクル
第2章 損益計算書(PL)の見方をマスターしよう!〔前編〕 2日目前半
利益はまぼろしに過ぎない
LECTURE01 損益計算書にダマされるな
●損益計算書とは何か?
●利益って何ですか?
●損益計算書はこうなっている
LECTURE02 損益計算書は、その1年間の価値の増減を表している
●収益って利益のことですか?
●期間利益はその期間に生成された価値のこと
●期間収益とは
●期間費用とは
●期間利益とは
COLUMN2 カットオフとは何か?
第3章 損益計算書(PL)の見方をマスターしよう!〔後編〕 2日目後半
費用の90%はたった10%の利益しかもたらさない
LECTURE01 会計は価値の増加が確定したタイミングを重視する
●3月31日に納品した商品の売上は、いつ計上されるの?
●減価償却は特殊な費用
●損益計算書を棒グラフで表現する
LECTURE02 損益計算書の中で最も重要な営業利益
●売上高総利益と売上高総利益率
●営業利益と営業利益率
●トヨタと日産は技術力が違うのか?
●経常利益と経常利益率
●税引き前当期純利益
●税引き後当期純利益
COLUMN3 減価償却費とは
第4章 貸借対照表は会社のふところ具合を表している 3日目前半
財務三表の中で最も重要な貸借対照表
LECTURE01 貸借対照表を見れば、その会社のふところ具合がわかる!
●貸借対照表はこうなっている
●会社にはお金が循環している
●全体を俯瞰することが大事
●資金の調達先は4つある
●他人資本は負債のこと
●自己資本は資本金・資本剰余金・利益剰余金を足したもの
LECTURE02 貸借対照表は、なぜ左右がバランスするのか?
●バランスシートのメカニズム
●利益剰余金は天秤のバランスをとる分銅だった!
●内部留保はどこにある?
●貸借対照表の資産は3つの部屋に分かれている
COLUMN4 貸借対照表が自動的にバランスすることの意味
第5章 貸借対照表はお金の流れのスナップショットだ 3日目後半
貸借対照表はお金の調達先と運用先を表している
LECTURE01 貸借対照表の右側で資金の調達先がわかる
●貸借対照表で会社の財政状態がわかる
●貸借対照表の資金の調達とは
●他人資本と自己資本の違い
●株式公開にはデメリットもある
LECTURE02 貸借対照表の左側で資産の運用状況がわかる
●資金の運用とは
●貸借対照表は決算日のスナップショット
●現金製造機とは固定資産のこと
●無形固定資産は見えない現金製造機
●知的資産を持つ会社は莫大な利益を稼ぐ
COLUMN5 現金取引と信用取引とは
第6章 貸借対照表で会社の安全性をチェックする 4日目
借金は少ないほどいいというものではない
LECTURE01 安全性分析とは何か?
●バランスシートの基礎知識
●短期的安全性とは
●運転資本は流動資産と流動負債の差額
LECTURE02 長期的安全性と財務レバレッジ
●長期的安全性
●固定比率
●固定長期適合率
●財務レバレッジ
●自己資本比率は財務レバレッジの逆数
COLUMN6 運転資本と正味運転資本
第7章 ROA(総資産利益率)とROE(自己資本利益率)をマスターする! 5日目
会社の命を削ってまでもROEを高めるべきではない
LECTURE01 お金の使い方が一目でわかる魔法の指標ROA
●経営者の能力を見抜く
●ROAが決算書分析の突破口だ!
●ROAを引き上げる
LECTURE02 株主が重視する指標はROE
●有能な経営者を見抜く指標もROE
●ROEを計算する
●借金漬けにするほどROEは高くなる
COLUMN7 債務超過の意味
第8章 キャッシュフロー計算書(CF)を理解する① 6日目
キャッシュフローは嘘をつかない
LECTURE01 キャッシュフロー計算書は最強の決算書
●現金(キャッシュ)は嘘をつかない
●なぜ経営者は粉飾決算に走るのか?
●キャッシュフロー計算書は1年間のお金の収支総額をまとめたもの
LECTURE02 キャッシュフロー計算書の仕組みを理解しよう!
●キャッシュフロー計算書の構造とは
●キャッシュフロー計算書は資金量が載っている
●キャッシュフロー計算書の3つの構造
●営業キャッシュフロー
●投資キャッシュフロー
●財務キャッシュフロー
COLUMN8 減価償却の自己金融機能とは
第9章 キャッシュフロー計算書(CF)を理解する② 7日目
利益がでていても、税金を払うお金がないのはなぜ?
LECTURE01 直接法による営業キャッシュフローを知る
●営業キャッシュフローは直接法と間接法の2つがある
●利益と営業キャッシュフローの違い
●直接法は理に適っているが欠陥がある
LECTURE02 間接法によるキャッシュフロー計算書をチェック
●間接法が一般的な理由
●間接法によるキャッシュフロー計算書
●現金の増減から間接法によるキャッシュフロー計算書を作成する
●運転資本が増えると、現金はその金額分少なくなる
●買掛金が増えると、なぜ運転資本は減るのか?
COLUMN9 期間利益重視の経営は正しいか?
第10章 キャッシュフロー計算書(CF)を理解する③ 8日目
投資を怠れば将来の儲けは確実に減り、競争から脱落する
LECTURE01 なぜ、投資が必要なのか?
●投資キャッシュフローは固定資産への資金運用と資金回収の差額
●フリーキャッシュフロー(FCF)は自由に使えるお金
LECTURE02 なぜ、会社は自社株式を取得するのか?
●財務キャッシュフローは資金の調達や返済、自社株買いなどの活動
●余ったお金の使い方
COLUMN 10 減価償却は多いほどいいのか? 赤字でも減価償却すべきか?
第11章 キャッシュフロー計算書(CF)を理解する④ 9日目
利益には質がある
LECTURE01 質の高い利益=アクルーアル(会計発生高)とは?
●損益計算書は本当に信じられないか?
●質の高い利益とは、現金の裏付けがある利益
LECTURE02 営業キャッシュフローを解読できるスキルを身につける
●営業キャッシュフローの典型的なパターンを覚えよう
●アクルーアルがプラスかマイナスかに注目
●営業キャッシュフローは嘘をつかない
●当期純損失になった理由
COLUMN 11 複式簿記は日本でも発明されていた?
第12章 これがわかれば会計のプロだ! 10日目
カノン、社長の父と対決する
応用編01 A社とB社では、どちらが儲かっているか?
●カノンは父親に勝てるのか?
●売上高と営業利益を比べてみると……
●税引き前当期純利益、総資産、自己資本を比べてみると……
応用編02 常識を超えた決算書は、どこが非常識なのか?
●常識を超えた決算書とは?
●貸借対照表をチェックしよう
●損益計算書をチェックしよう
●キャッシュフロー計算書をチェックしよう
●カノンと涼之助の答えは?
●膨大な利益のほとんどを配当と自己株式の買い入れに使っている
●投資有価証券であり余る現金を運用している
●目に見えない現金製造機が働いている
●儲かりすぎているから、わざと借金をしている!?
著者
林總(はやし・あつむ)
公認会計士、税理士
明治大学専門職大学院 会計専門職研究科 特任教授
LEC会計大学院 客員教授
1974年中央大学商学部会計学科卒。同年公認会計士2次試験合格。外資系会計事務所、大手監査法人を経て1987年独立。以後、30年以上にわたり、国内外200社以上の企業に対して、管理会計システムの設計導入コンサルティング等を実施。
2006年LEC会計大学院 教授、2015年明治大学専門職大学院 会計専門職研究科 特任教授に就任。
著書に、『餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか?』『美容院と1,000円カットでは、どちらが儲かるか?』『コハダは大トロより、なぜ儲かるのか?』『新版わかる!管理会計』(以上、ダイヤモンド社)、『ドラッカーと会計の話をしよう』(KADOKAWA/中経出版)、『ドラッカーと生産性の話をしよう』(KADOKAWA)、『正しい家計管理』(WAVE出版)などがある。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)