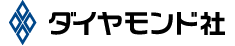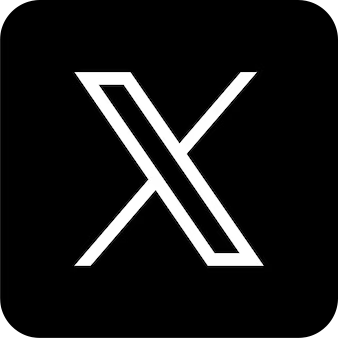失敗は「そこ」からはじまる

失敗は「そこ」からはじまる
書籍情報
- フランチェスカ・ジーノ 著/柴田裕之 訳
- 定価:1980円(本体1800円+税10%)
- 発行年月:2015年01月
- 判型/造本:46並製
- 頁数:360
- ISBN:978-4-478-02538-3
内容紹介
わざわざ顧客を裏切る決定をしたコカ・コーラ、忠告を無視して歴史的大失敗をしたサムスン……。なぜ我々の意思決定は、目指すべき目標からかくも簡単に「脱線」してしまうのか?人間心理と組織行動の両方を究めたハーバード・ビジネススクール人気教授が、人と企業が成功するための意思決定の「9つの原則」を解き明かす。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
序章 なぜ私たちは、「成功」をみすみす逃す意思決定をしてしまうのか?
ドバイ旅行を台無しにした「完璧な模造品」
私たちの計画は、なぜこうも簡単に「脱線」してしまうのか?
東京ディズニーランドが土産物店を増やさない理由
偽クロエのサングラスが人を「嘘つき」に変える?
部屋の明るさ、コーヒーの苦さ……成功と失敗の「分岐点」はいたるところに
第1部 「内なる自分」──自分の内面に由来する力
第1章 なぜグリーンスパンは、サブプライムローンの危険性を見抜けなかったのか?
──不正確な自己イメージに「気づかない」
クイズ番組のジレンマ──「オーディエンス」を信用しない解答者
ウォルマートの「避けられた失敗」──なぜCEOは「貴重な助言」を無視するのか?
他人の意見はいついかなるときも不正確?
87%の人が「マザー・テレサより素晴らしい」と答えた人物って誰?
あなたの「自信過剰度」を計るシンプルなテスト
高くついたグリーンスパンの過信──権力は人を自己中心的にする
コンサルタントの助言は、「高額だから」ありがたい?
「助言の重み」は、かかったコストの多寡で決まる
「専門家」の意見を無批判に受け入れていないか?
〈原則1〉セルフイメージ──自己認識の「歪み」を自覚する
第2章 マイクロソフトのヤフー買収提案額は本当に「少なすぎた」のか?
──伝染する感情に「流される」
ジェリー・ヤンの意思決定は合理的、それともただの強情?
感情が意思決定を脱線させる
朝の交通渋滞のイライラが、その日1日の決断を支配する?
他人のアイデアを批判するときはご注意あれ──「付随的な」怒り
幸せなことを思うと幸せになる──感情の「帰属の誤り」
感謝されたから、人助けする──因果関係は実は逆だった?
オートバイレースで勝つのに「レーサーの意見」はいらない!?
赤の他人の顔色1つで意思決定は狂う──感情の伝染
〈原則2〉エモーション──感情の「体温」を測る
第3章 なぜサムスンにだけ「そのリスク」は見えていなかったのか?
──視野が狭すぎて「見落とす」
寓話「2つの鍋」とサムスン自動車の歴史的大失敗
そこにいるのに見えない「ゴリラ」──超有名な実験と「非注意性盲目」
「裁判に勝ちさえすれば……」──大手保険会社ユーレコが陥った視野狭窄
話す相手がすり替わっても気づけない!?──「変化に対する盲目」
会計士に気づかれずに不正を行う方法
優れたツールを使った2チームの相反する結果──弊害①全体像を見失う
タッピングで「歌」を伝えられますか?
なぜメールだと自己中心的になりがちなのか?──弊害②手持ちの情報の過大評価
中古車売買実験でわかった「交渉の盲点」──弊害③制約の過小評価
〈原則3〉フォーカス──ズームアウトして「視野」を広くとる
第2部 「まわりの人」──他者との関係に由来する力
第4章 なぜコカ・コーラは顧客を裏切る意思決定をしたのか?
──相手視点の欠如で「しそこねる」
額にどう「E」の字を書くか?──ある「能力」を調べる単純なゲーム
顧客ロイヤルティを失った「自分本位」の広告戦略
コカ・コーラが理解しそこなった「強烈な愛着」
「自分ばかりが家事をしている」は本当か?
初心者への説明がこうも難しい理由──「知識の呪い」
「心をこめた贈り物」でがっかりされるのはなぜ?──プレゼント問題①
誰にもらったかで価値が変わる?──プレゼント問題②
「新人が質問しない」という人類共通の悩みを一発で解決する実験
〈原則4〉ビューポイント──相手の「視点」にスイッチする癖をつける
第5章 ITベンチャーが失敗するのは「友情」の過大評価のせい?
──油断ならない社会的絆に「影響される」
ひいきのチームはいつだって反則しない?
グーグル、アップル、ヤフー……ビジネスと友情は両立するか?
灰色のTシャツの呪い──不正も不合理も「仲間がやってるならOK」
「よそ者」との競争が抗争を生む──内集団と外集団
「名字が同じ」というだけで道徳規範を踏み外す
タオルの再利用率を上げるには?──「自分と似た人たち」の影響力を正しく使う
〈原則5〉リンク──社会的な「つながり」の影響力を把握する
第6章 フェイスブックをチェックするたびに「少し焦る」のはなぜ?
──あからさまな社会的比較で「のせられる」
星形シールの威力──私を熱心なジム通いに変えた「社会的比較」
新生銀行子会社「アプラス」での実験──フィードバックがやる気に火をつける
悲しいかな、人は比べずに自分を知ることはできない
トム・ハンクスの悲劇──人は自分より優秀な人を推薦しない
フェイスブックの「友達リスト」という恐るべき比較装置
お金の魔力──人をいともたやすく「格付け」する
整備工は高級車ほど手を抜く──富とインセンティブ
富裕/貧困実験でわかった人間の本質
嫉妬に悩まされるぐらいなら、嘘・不正・損失を選ぶ!?
〈原則6〉ランキング──自分の「評価基準」を問い直す
第3部 「取り巻く社会」──外の世界に由来する力
第7章 「研究開発費」が多ければイノベーションが起こりやすい、は本当か?
──的外れの情報で「決めつける」
フィジー政府の誤謬──その飲料水メーカーは本当に儲かっていたのか?
目に見える情報だけで相手を「わかったつもり」になる──①対応バイアス
クイズ番組「出題者優位」の法則
「一流校の平均」よりも「三流校の首席」のほうが価値が高い?
昇給への道は、「努力した」と思い込ませることにあり──②投入バイアス
プロセスの評価は結果次第で180度変わる──③結果バイアス
よい結果が出ているうちは不正もまかりとおる?
積みあげた書類の「山」と生産性の高さを混同する
〈原則7〉インフォメーション──情報とその「出どころ」を多面的に確認する
第8章 ディズニーが社員を「キャスト」に変える魔法の正体は?
──フレーミングによる微妙な変化に「ハメられる」
プリンを買ってヨーロッパへ──フレーミングで155万マイルを手にした男
「10杯飲むと1杯無料」をより魅力的に言い換えられるか?──「付与された進捗効果」
街にあふれる「細かい選択肢」が判断を鈍らせる──カテゴリーの力
SNSをすぐにチェックするよう仕向ける「恐れ」の正体とは?
どんな「メニュー」を作れば注文が増えるのか?
御社の研修とディズニーの研修を分かつものとは?
新人研修のフレーミング次第で「離職率」は60パーセント下がる
有権者に投票所に行かせる質問の仕方
〈原則8〉フレーミング──選択肢の「型」を見破る
第9章 不正をした政治家やCEOは、なぜ平然と正当化できるのか?
──状況の力と自己欺瞞の誘惑に「そそのかされる」
なぜ照明を増やせば犯罪は減るのか?
サングラスをかけるだけで…… ──「架空の匿名性」という感覚
現代版「善きサマリア人」実験──道徳心を曲げる「状況」の力
人は誰でも詐欺師になる──金持ちを目の前にすると聞こえる「悪魔のささやき」
ドーピングを見事に正当化したメジャーリーガー ──「自己欺瞞」という罠
カンニングするとかならず起こる「壮大な勘違い」
「道徳的偽善」──努力もせずに善人だとうぬぼれる
正邪のグレーゾーンで、公正な意思決定は可能なのか?
〈原則9〉シチュエーション──状況の力から自分の「基準」を守る
まとめ 「9つの原則」で失敗しない意思決定を
リュディアの賢王が教えてくれる「計画」の力
まずは脳に「バグ」があることを認めよう
脱線しなければ、交渉もダイエットもうまくいく
意思決定で失敗しないための9つの原則(復習)
フォルクスワーゲンと「愉快なセオリー」──「脱線防止」システムを作る
気づくことからすべては始まる──意思決定でもう後悔しないために
謝辞
訳者あとがき
注記
索引
著者
フランチェスカ・ジーノ(Francesca Gino)
ハーバード・ビジネススクールの経営学准教授(交渉術・組織・市場ユニット)。
イタリア出身。経済学・経営学の博士号(Ph.D.)を持ち、ハーバード大学、カーネギーメロン大学等での講師を経て現職。他にも、ハーバード・ロースクールの交渉学プログラム、及びハーバードの「心・脳・行動イニシアティブ(Mind, Brain, Behavior Initiative)」にも正式に関わっている。
意思決定や社会的影響、倫理観、モチベーション、創造性と生産性などを研究対象とし、経済学や経営学、交渉学といった枠組みを超え、社会心理学、行動経済学、組織行動学など、幅広い研究者と積極的に共同研究を行っている。研究成果を広く一般に伝えることにも注力しており、心理学と経営学の一流学術誌だけではなく、「ニューヨーク・タイムズ」、「ウォールストリート・ジャーナル」、「ビジネスウィーク」、「エコノミスト」、「ハフィントンポスト」、「ニューズウィーク」、「サイエンティフィック・アメリカン」など、さまざまな一般向け刊行物にも取りあげられている。また、得られた組織行動や意思決定の知見をもとに、企業や非営利団体のコンサルタントとしても活躍している。マサチューセッツ州ケンブリッジ在住。http://francescagino.com/
訳者
柴田裕之(しばた・やすし)
1959年生まれ。翻訳者。訳書にポール・J・ザック『経済は「競争」では繁栄しない』(ダイヤモンド社)、マット・リドレー『繁栄』(共訳、早川書房)、マイケル・S・ガザニガ『人間らしさとはなにか?』(インターシフト)、フランス・ドゥ・ヴァール『共感の時代へ』『道徳性の起源』、エイドリアン・ベジャン&J・ペダー・ゼイン 『流れとかたち』、ダニエル・T・マックス『眠れない一族』(以上、紀伊國屋書店)、ジョン・T・カシオポ他著『孤独の科学』(河出書房新社)ほか多数。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
- kobo
- kindle
- COCORO BOOKS
- Reader Store
- 紀伊國屋書店Kinoppy
- honto
- Booklive!
- セブンネットショッピング
- Google Playブックス
- Apple Books
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)
内容紹介
コカ・コーラ、サムスン、ヤフー創業者……
綿密に計画したはずなのに、
「あの人、あの会社が、なんでそんなことを?」
ハーバード・ビジネススクール人気教授が提言する意思決定「9つの原則」
|
→ヤフー創業者がわざわざ170億ドルも損する選択をしたのはなぜ? |
綿密に計画を練り上げて意思決定をしたはずなのに、
気がついたら違う行動をしていた、という経験はないだろうか?
新しいキャリアを切り拓くために勉強しようと決めたのに先延ばしにし、
ダイエットを決意したのに翌日にはサボり、
老後のために立てた貯蓄計画は日々の散財でダメになり、
顧客ロイヤルティを高めるための新しいマーケティングプランはまったく逆の結果に終わり……。
そう、私たちは往々にして、当初思い描いた計画から「脱線」し、
そのせいですぐそこにあったはずの成功を逃してしまいがちだ。
そしてその結果にがっかりし、やる気を失ってしまう。
私たちの意思決定は、どうしてこれほど頻繁に脱線してしまうのだろうか?
どうすれば、軌道から外れないようにできるのか?
過去10年、この疑問に答えることに的を絞った研究プロジェクトをいくつも行い、
人間心理と組織行動の両方を究めた新進の研究者にしてコンサルタントが、
意思決定の失敗の本質、そしてブレずに成功するための「9つの原則」を解き明かす。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
- kobo
- kindle
- COCORO BOOKS
- Reader Store
- 紀伊國屋書店Kinoppy
- honto
- Booklive!
- セブンネットショッピング
- Google Playブックス
- Apple Books
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)