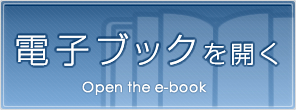セコム その経営と真髄 page 7/12
このページは セコム その経営と真髄 の電子ブックに掲載されている7ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
49 第1章 創業者・飯田亮の生い立ちと、創業に至るまで人ほどいた。裕福で賑やかな大所帯で、皆から亮まことを縮めて「マコ」と呼ばれ可愛がられたが、父母には厳しく育てられた。たとえば、父からは「しゃがむな....
49 第1章 創業者・飯田亮の生い立ちと、創業に至るまで人ほどいた。裕福で賑やかな大所帯で、皆から亮まことを縮めて「マコ」と呼ばれ可愛がられたが、父母には厳しく育てられた。たとえば、父からは「しゃがむな。しゃがんでいる人の顔を見ろ。だらしない顔つきをしているだろう。ああなるぞ」、母からも「ため息をつくな」、と大きな声で叱られた。 父母とも「後ろ向きな気持ち」は、かけらたりとも許さなかった。「三つ子の魂百までも」と言うが、疲れたからといって決して一服しない、ため息をついて落ち込むようなことをしない、企業家にとって最も大切な「商人の精神」を、小さい頃から家庭で叩き込まれていたのである。 経営者に限ったことではないが、人は時代とともに生きる動物である。本人だけでなく、時代の影響を受けて生きる親に育てられ、時代の中で生きる人々と交わることで「時代の意識」を形成する。その時代の刺激が強ければ強いほど、変化が大きければ大きいほど、自分を真剣に見つめ社会に対して敏感になるものだ。 近現代では、明治維新を挟んで生きた人々や、飯田氏のような「戦中派」は、パラダイムの転換を経験した世代である。(第二次世界大)戦前、戦中、戦後は、「企業家・飯田亮」を形成する上でも大きな影響を及ぼしている。飯田氏だけでなく、明治期と戦後は、創業ラッシュの時代であった。明治期には財閥が形成され、日本の資本主義の礎が築かれた。そして戦後は、焼け跡になった地から、ホンダやソニーといった「焼け跡派ベンチャー」が生まれた。それに続く第二世代として、昭和30年代にセコムや京セラが誕生した。