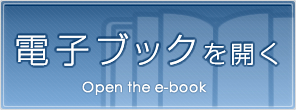セコム その経営と真髄 page 6/12
このページは セコム その経営と真髄 の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
48っても過言ではない。まず、はじめに、「代表者」として異彩を放つ飯田氏の、誕生してから起業に至るまでの経緯をたどっていくことにしよう。「企業家・飯田亮」を形成した青春時代 飯田氏は1933(昭和8)年....
48っても過言ではない。まず、はじめに、「代表者」として異彩を放つ飯田氏の、誕生してから起業に至るまでの経緯をたどっていくことにしよう。「企業家・飯田亮」を形成した青春時代 飯田氏は1933(昭和8)年4月1日、父・飯田紋治郎、母・なつの五男として生まれる。男ばかりの末っ子として育った。生家は、江戸時代から続き、現在、東京・日本橋馬喰町で酒問屋を営む岡永商店(現・岡永)である。屋号の「岡本屋」と祖父永吉の名をとった。「江戸っ子」に確固たる定義があるわけではないが、「三代続いて江戸(東京)に住めば江戸っ子」というのであれば、飯田氏は由緒正しき江戸っ子と言える。ただし、江戸幕府を開いた徳川家康が三河(現・愛知県東部)出身で、同地域の人々がたくさん江戸へ移り住んだ。飯田家も江戸時代に、一族揃って三河から江戸へ移住したらしい。 セコムは社会の変化を予測し伸びてきた会社だが、飯田家も機を見るに敏な血筋である。祖祖父は江戸時代に油問屋を営み、明治になりガス灯が出現すると油に見切りをつけ、味噌、醤油、酒の小売を始めた。そして、父の代に卸売業に転じた。 飯田氏が幼少の頃、岡永商店には丁稚奉公の小僧さん、女中さんなどが住み込み、従業員が30